|
|
| ���@�{�݂̊O�� |
�}������Â̒��j�a�@�Ƃ��Ēn���Â��x����
�@���Q���l�������s�ɂ���Љ��Ö@�l�ΐ�L�O��HITO�a�@�́A�u��������x����v���R���Z�v�g�ɁA���a�����łȂ��A�l��f��Ƃ������_��厖�ɂ��Ȃ���A�u�N������I��A�M�������a�@��ڎw���v���Ƃ��~�b�V�����Ɍf���Ă���B
�@�@�l�̉��v�Ƃ��ẮA���a51�N�ɐΐ�O�Ȉ�@���J�@�������Ƃɂ͂��܂�B���a54�N�ɑO�g�ƂȂ�ΐ�a�@���J�݂��A�n��̋~�}��Â��x���������S���Ă����B���̌�A���Q���n���ÍĐ��v��ɂ�錧���O���a�@�̖��Ԉڏ��ɔ����A104���̑������āA����25�N4���ɎЉ��Ö@�l���ƂƂ��ɁA�V�a�@���J�݂��ĕa�@����HITO�a�@�ɉ��̂����B
�@����ɁA���@�l���܂ށA��Ö@�l���N��A�Љ���@�l������Őΐ�w���X�P�A�O���[�v���`�����A�n��ɍ����������l�Ȉ�ÁE���E�����T�[�r�X��W�J���Ă���B
�@���݂̕a������228���ŁA���̓���͋}�����a��86���i�}������ʓ��@��1�j�AHCU�i���x��Áj12���ASCU�i�]�����W�����Î��j6���A�����a��4���A�n���P�A�a��53���A�ɘa�P�A�a��17���A�����n�r���e�[�V�����a��50���ƂȂ��Ă���B
�@�a�@�̐v�ł́A�⎆�Ȃǘa�̑f�ނ������������R�̐F����Ƃ����f�U�C�����̗p���A���ҁE�Ƒ������������₭�났�����������Ԃ���Ă���B
�@����܂œ��@���n��ŒS���Ă�����Ë@�\�ɂ��āA�������̐ΐ��㎁�͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u���@����������F����Ì��̐l���́A�J�@���̖�10���l���猻�݂�8��2,000�l�ɂ܂Ō������A�ߘa22�N�ɂ͐��Y�N��l����3���������邱�Ƃ����v����Ă���A����͐l�������ƂƂ��ɁA������̊m�ۂ����Ɍ������Ȃ�Ƃ����ۑ肪����܂��B���̂悤�ȂȂ��A���@�͊J�݈ȗ��A2���~�}�a�@�Ƃ���24����365���̐��ŋ~�}�f�Â��s���A�N��2,200������~�}�����������ƂƂ��ɁA4���a�i�]�����A����A�S�����A���A�a�j�̃Z���^�[�@�\��L���A�]�����A�S�����ɂ��Ă͈�Ì����ŗB��~�}�Ή����\�Ȏ{�݂ƂȂ��Ă��܂��B���̈���ŁA�n��̍���̐i�s���������A�����i�K���烊�n�r����ɘa�P�A�A�ݑ��Âɂ��͂����A�P�A�~�b�N�X�a�@�Ƃ��Ă̋@�\���������Ă��܂��v�B
|
|
|
| ���@HITO �a�@�̑�����t | ���@�����������̗p�����z�X�s�^���X�g���[�g�́A�J���I�ȗ��������̂����ԂƂȂ��Ă��� |
 |
|
| ���@�}�����a����4�����B�v���C�o�V�[�ɔz���������ŗ×{���邱�Ƃ��ł��� | ���@�ɘa�P�A�a���ɐݒu�����k�b���B���܂��܂ȏ������������Ă���A�Ƒ��⊳�ғ��m�����낢�Ō𗬂ł����Ƃ��Ċ��p���Ă��� |
 |
|
| ���@�ŏ�K��11 �K�ɐݒu�������X�g�����́A�s���̌i�F����]���邱�Ƃ��ł��� |
�Ɩ��p�`���b�g�����p������L
�@���@�́A�����i�K����f�W�^���@��̓����A���DX�̎��g�݂𐄐i���Ă���B���g�݂̈�Ƃ��āA�X�^�b�t�ɃX�}�[�g�t�H������A�Ɩ��p�`���b�g�����p������L��Θb�ɃV�t�g���邱�Ƃɂ��A�Ɩ��̌������ƂƂ��Ɏ��̍�����ÒɂȂ��Ă���B
�@�f�W�^���@��̓����E���DX�Ɏ��g�o�܂ɂ��āA�]�_�o�O�ȕ����EDX���i��CXO�̎��������͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u����29�N�ɔ]������Âɂ����āA��̔]�_�o�O�Ȉオ2�l���玄1�l�ɂȂ������Ƃ����������ł����B���Ȃ��l����24���ԑ̐��̋~�}��Â��ێ����������Ƃ��Ĕ]�_�o�O�ȃ`�[���ŋƖ��p�`���b�g�����p������L���Ă��܂����B���ɁA�������C���Ă������n�r���e�[�V�������ŊJ�n���A����܂Ŗ���20���ȏ�s���Ă�������E�I���p�~���A�`�[���`���b�g�ɂ��E�A���E���k�Ȃǂ̏�L�ƑΘb�ɃV�t�g�����Ƃ���A��t�̃X�g���X���y�����A�X�^�b�t����t����v���ɏ��F���Ƃ��ق��A�X�}�z�œd�q�J���e���{���ł��邱�Ƃɂ��A�Ɩ��̌�������}�邱�Ƃ��ł��܂����B���̌��ʁA���҂ւ̃��n�r�����Ԃ������A���n�r���P�ʐ��̑����ɂ�鑝�����Ń����j���O�R�X�g��P�o���邱�ƂɂȂ���܂����v�B
|
|
|
| �]�_�o�O�ȕ��� CXO-CHRO �� ���� �� | �o�c�헪�{�� CIO DX���i�� ���� ���� �� �� |
�R�~���j�P�[�V�����̎��E�ʂƂ��Ɍ���
�@���̐����̌������ƂɁA�i�K�I�ɑ�����ɍL���A���݂͂��ׂĂ̕���ň�l���̃X�}�z����A�`�[���`���b�g�𐄐i���Ă���B
�@�`���b�g�ɂ����`�B���L�́A�Ɩ��̌����������łȂ��A�`�[���`���b�g�̃��b�Z�[�W����������3�N�ԂŖ�20�{�i�N��20�����j�ƂȂ�A�R�~���j�P�[�V�����̗ʁE���Ƃ��ɏオ���Ă���Ƃ����B
�@�u�Ƃ��ɎႢ�X�^�b�t�͌o����m�������Ȃ����߁A�Ζʂł͎����̈ӌ��������Â炢�Ƃ��낪����܂������A�`���b�g�ɂ����`�B�ł̓X�}�z�ɓ��ڂ��������`�h��l�b�g�Œ��ׂĔ��M�ł��邽�߁A�ӌ����Ă����₷���A�R�~���j�P�[�V�����̃X�g���X���y�����Ă���Ǝv���܂��B�`�[���`���b�g�̃��b�Z�[�W���e�́A�X�^�b�t����̒�Ă�˗��������ȏ���߂Ă���A��Ă������e�����F����邱�ƂŎ��ȍm�芴�������A����ɒ�Ă���Ƃ����D�z�����܂�Ă��܂��v�i�����j�B
�@�`�[���`���b�g�̃����o�[�ɂ́A��t�A�Ō�t�A�Z���s�X�g�A��t�A�Ǘ��h�{�m�Ȃǂ̐��E������A�ӌ����ĂȂǂ̏������L���Ă��邽�߁A���������ʂ������ă`�[����Â����������邱�ƂɂȂ����Ă���Ƃ����B
|
|
| ���@�X�}�z�̃`���b�g�@�\�����p������L�ƑΘb�ɂ��A�Ɩ��̌������ƃR�~���j�P�[�V�����̎��Ɨʂ�����I�Ɍ��サ�� |
�x�b�h�T�C�h�𒆐S�Ƃ����V���ȃP�A�V�X�e��
�@�X�}�z�����p�����d�q�J���e�̉{�����L�ɂ��Ɩ��̌������ɂ��A�X�^�b�t�̓x�b�h�T�C�h�ɑ؍݂��鎞�Ԃ����������Ƃ��A���@�ł͏]���̕a���̐���ς��A�V���Ɂu���E�틦���Z���P�A�V�X�e��(R)�v���\�z�����B
�@��̓I�ɂ́A�a����3�́u�Z���v�ɕ����A���ꂼ��́u�Z���v�ɑ��E��ɂ�鏬�K�͂Ń����o�[���Œ肵���`�[����z�u���A�x�b�h�T�C�h�𒆐S�ɋƖ����s���̐������邱�ƂŁA���҂̌ʐ��ɂ��킹���A��莿�̍����P�A����Ă���B
�@�`���b�g�ɂ���L��V���ȃP�A�V�X�e���̑̐����\�z�������ʂƂ��āA�X�^�b�t��1��������̈ړ�������4�`5�q�������A1��100���̎��Ԃ�n�o���邱�Ƃ������B�Ō�t�S�̂̎��ԊO�J���͔N��6,000���ԍ팸����A�J�����̉��P�ƂƂ��ɁA�o�c�ɂ��悢�e���������炵�Ă���B
�@�܂��A���@�ł͑����̊O���l�̊Ō�⏕�҂���X�^�b�t���ٗp���Ă���A�`���b�g�Ɏ����|��@�\��g�ݍ��ނ��ƂŁA���{��̕��͂��ꍑ��ɕϊ�����A���t�̕ǂ��ē������Ƃ��\�ƂȂ����B�O���l�Ō�⏕�҂���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ�A�}�����a���̊Ō�⏕�̐����Z���Z�肷�邱�Ƃ��ł��Ă���Ƃ����B
�@�u���@�̈��DX�̎��g�݂����f�B�A�Ɏ��グ�Ă�����������A���甭�M���邱�Ƃɂ��A���O������E����]���錤�C���Ō�t��������ȂǁA�l�ފm�ۂɂ����ʂ��o�Ă��܂��B�R���i�Ђɂ����Ă��V�l�Ō�t��1�l�����E�҂��o�Ȃ��������Ƃ͋����ł������A�蒅�ɂ��Ȃ����Ă��邱�Ƃ͑傫�Ȑ��ʂ��Ǝv���܂��v�i�ΐ엝�����j�B
 |
|
| ���@�X�}�z�Ɏ����|��@�\��g�ݍ��ނ��ƂŁA�O���l�X�^�b�t�����t�̕ǂ��Ȃ��A�`���b�g�ł̏�L���\�� | ���@�a���O�ł̃Z���J���t�@�����X�̗l�q�B�Ɩ��̌������ɂ��A�x�b�h�T�C�h�̑؍ݎ��Ԃ������A��莿�̍����P�A�̒����� |
�X�}�[�g�O���X�����p�������u�x��
�@����ɁA���@�ł͈��DX�̎��g�݂Ƃ��āA�V���Ɂu�X�}�[�g�O���X�v�����A���u�x���ɂ���ÃX�^�b�t�̗L�����p�╉�S�y���A�X�L���̌����}���Ă���B
�@�X�}�[�g�O���X�́A���K�l�̂悤�ɑ�������E�F�A���u���f�o�C�X�ŁA���ڂ������^�J�����A�X�s�[�J�[�ɂ��A�����҂̎��_�f�������u�ŋ��L���邱�Ƃ��ł��A�f���Ȃǂ̏����X�}�[�g�O���X�̎��E�ɕ\�����邱�Ƃɂ��A�n���Y�t���[�ō�Ƃ��s�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B
�@���@�ł́A��ɖK��f�Â�K��Ō�ȂǍݑ��Â̌���Ŋ��p���Ă���A���҂̏�Ԃ����u�Ŋm�F������A���������Ƃ�����Έ�t���w���≓�u�x�����s���Ă���B����ɁA�X�}�[�g�O���X�ɂ͘^��@�\������A�X�^�b�t�̃X�L���A�b�v��}�鋳�瓮��Ƃ��Ċ��p���Ă���Ƃ����B
�@���̂ق��ɂ��A�O���[�v�@�l���^�c������{�݂ŁA�H���������l�q���@���̌��꒮�o�m���m�F���Ďw�����s�����Ƃɂ��A�K�ȃP�A�̒�뚋���x���Ȃǂ�h�~���邱�ƂɎ��g��ł���B
�@�܂��A��ΑтŖڂ������Ȃ����҂ɁA�x�b�h�T�C�h�ɌŒ�J������ݒu���鋖�����炢�A�Ō�t�̓n���Y�t���[�ŕʂ̍�Ƃ��s���Ȃ���A�X�}�[�g�O���X�ʼnf�����m�F���ĉ��u�ł̌�����ً}�Ή��̕K�v���f�ł��邱�Ƃɂ��A���S�y����}���Ă���B���݂́A���̎��g�݂ɂ��Č����J���Ȃ̎��؎��ƂƂ��āA�X�}�[�g�O���X�����p�������҂̉��u�����ɂ��Ō�t�̕��S�y���Ɋւ�����ʌ������{���Ă���B
�@�u���DX�𐄐i���Ă��������ł̃|�C���g�Ƃ��ẮA��������̂ł͂Ȃ��A���S�̂������Ă��镔��ɑI�����̈�Ƃ��ē������A�֗����Ǝv�����X�^�b�t�����p���͂��߂āA���R�ɐ�ւ���Ă�����������邱�Ƃ��d�v�ł��B���Ƃ́A���܂܂ł̂������c���Ȃ���A���K�͒P�ʂŊJ�n���邱�ƂŃR�X�g������قǂ����炸�A���X�N�����Ȃ��Ȃ�܂��v�i�����j�B
 |
| ���@�X�}�[�g�O���X�����ċƖ����s���l�q�B���p�҂̎��_�f�������u�ŋ��L���邱�Ƃ��ł��� |
����̈�Ï�����������a���̃_�E���T�C�W���O
�@���@�́A�ߘa6�N1���ɋ}�����a�������������A�a������257������228���Ƃ���_�E���T�C�W���O��}�����B
�@�u���������}�����a���̉ғ�����90���O��Ő��ڂ��A����قǗ����Ă����킯�ł͂���܂��A����̈�Ï�⓭����̊m�ۂ�����ɂȂ邱�ƁA�݉@�����̒Z�k�Ȃǂ̏ɂ��킹�Ă����K�v������ƍl���܂����B���R�A�_�E���T�C�W���O������Ǝ��v��������܂����A���DX�𐄐i���Ė��x�̍����P�A����邱�Ƃɂ��A�ғ����Ɖ�]�������܂邱�ƂŒP�����オ��A���v��ۂ��Ƃ��ł��Ă��܂��B����A�a�@�̓X����������A����ɍ݉@�������Z�k���Ă����܂��B�����Ȃ��Ă���ƁA���S�͍ݑ��ÂɂȂ�A�V�[�����X�ȘA�g��a�@�̐��E��n��̂Ȃ��ŗL�����p������A�ݑ��Â��a���̈ꕔ�Ƒ����ēW�J���Ă����K�v������܂��B�X�}�[�g�O���X�̊��p������������������g�݂ƂȂ�܂��v�i�ΐ엝�����j�B
�@�f�W�^���@��̓����A���DX�̐��i�ɂ��A�Ɩ��̌������ƂƂ��Ɏ��̍�����Ò��������铯�@�̍���̎��g�݂����ڂ����B
�@
�Љ��Ö@�l�ΐ�L�O��@HITO�a�@
�������@�ΐ�@���@��
 �@���݂̉ۑ�Ƃ��ẮA�����^�̑g�D�ɂ��Ă������߁A���ꂼ��̓��ӕ������������悤�ɁA���E�Ƒg�D���f�I�ɓ����l�ނ����z�u���l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���݁A�O���[�v�ɂ�3 �@�l������A���ꂼ��Ɏ�����������Ă��܂������A�ߘa5�N�Ɉ�ʎВc�@�l�𗧂��グ�A�����A�l���A�L��̐l�ނ��W�A�{���@�\���������邱�ƂŁA3�@�l���}�l�W�����g���m������̐������Ă��܂��B
�@���݂̉ۑ�Ƃ��ẮA�����^�̑g�D�ɂ��Ă������߁A���ꂼ��̓��ӕ������������悤�ɁA���E�Ƒg�D���f�I�ɓ����l�ނ����z�u���l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���݁A�O���[�v�ɂ�3 �@�l������A���ꂼ��Ɏ�����������Ă��܂������A�ߘa5�N�Ɉ�ʎВc�@�l�𗧂��グ�A�����A�l���A�L��̐l�ނ��W�A�{���@�\���������邱�ƂŁA3�@�l���}�l�W�����g���m������̐������Ă��܂��B�@�ǂ����Ă��A�{�̕����̕a�@�ŗ��v���o�����Ƃ�����Ȃ��Ă���̂ŁA�z�[���f�B���O�X�ŐV�K���Ƃ���|���Ă����Ȃ���A����͎��x������Ȃ��Ȃ�\��������Ǝv���Ă��܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| �a�@�J�� | ����25 �N�i�O�g�a�@�F���a51 �N�j | ||
| ������ | �ΐ�@��� | �a�@�� | �ɓ��@�� |
| �a���� | 228 ���i�}������ʓ��@��1�@86���AHCU 12���ASCU 6���A�����a�� 4���A�n���P�A�a�� 53���A�ɘa�P�A�a�� 17���A�����n�r���e�[�V�����a�� 50���j | ||
| �f�É� | ��������ȁA�z����ȁA�]�_�o���ȁA�ċz����ȁA�ɘa�P�A���ȁA���A�a���ȁA���E�}�`�ȁA�O�ȁA�~�}�ȁA���B�O�ȁA������O�ȁA�S�����NJO�ȁA�ċz��O�ȁA���O�ȁA�]�_�o�O�ȁA���`�O�ȁA�`���O�ȁA���e�O�ȁA�w�l�ȁA��A��ȁA���@��A�ȁA�畆�ȁA���n�r���e�[�V�����ȁA���ː��ȁA�����ȁA���ȁA���_�� | ||
| �ΐ�w���X�P�A�O���[�v | ��Ö@�l���N��A�Љ���@�l������ | ||
| �Z�� | ��799-0121�@���Q���l�������s�㕪��788 �Ԓn1 | ||
| TEL | 0896�|58�|2222 | FAX | 0896�|58�|2223 |
| URL | http://hitomedical.co-site.jp// | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2025�N1�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B


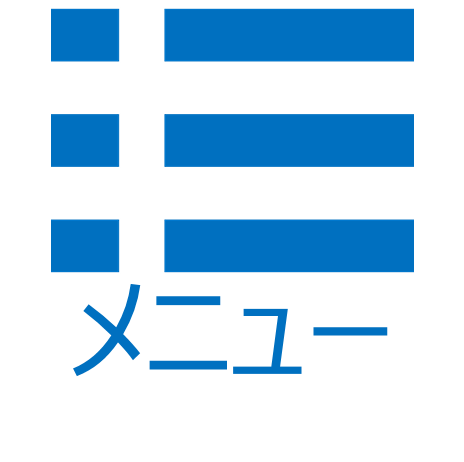

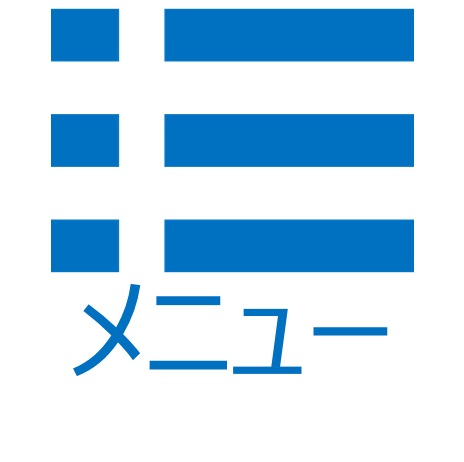
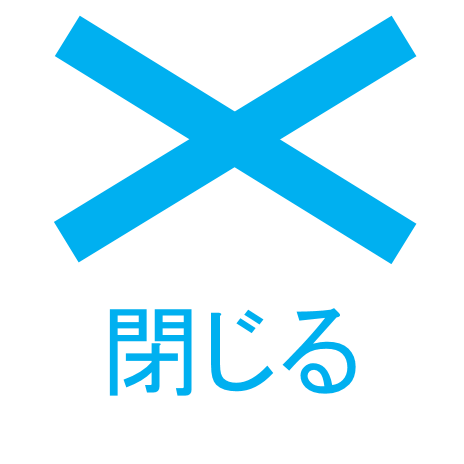
 WAM NET�����p�K�C�h
WAM NET�����p�K�C�h
