|
|
| ���@�{�݂̊O�� |
���҂𒆐S�ɒn��Ɋ��Y���P�A���Ƃ�W�J
�@�a�̎R�s�_�ɂ����Ö@�l�v�m��F�s�{�a�@�i�������F�F�s�{�@�v���j�́A�uHand in Hand�v�Ƃ����a�@���O�̂��ƁA���҂𒆐S�ɒn��Z���Ɋ��Y�����P�A���Ƃ�W�J���Ă���B
�@���a45�N�ɊJ�݂������@�́A�������E����ÁA�ݑ��Âɗ͂����Ă���B���݂̕a������80���ŁA���̓���͈�××{�a��44���A�n���P�A�a��36���ƂȂ��Ă���B����ɁA�@�\�����^�ݑ�x���a�@�̎w����A�n��̐f�Ï��̃o�b�N�x�b�h�Ƃ��Ă̖�����S���ƂƂ��ɁA�n��̈�Ë@�ցA�K��Ō쎖�Ə��Ɓu�킩��܍ݑ��Ãl�b�g���[�N�v���`�����A�a�̎R�s���ŔN�ԉ���1���l�ȏ�̍ݑ�×{���T�|�[�g���Ă���B
�@�a�̎R�s�̐l�����Î��v�̏ɂ��āA���������̉F�s�{�z�q���͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u���@�����n����a�̎R�s�̐l���́A�������ݒn�ł���Ȃ���A���a60�N��40���l���s�[�N�Ɍ��݂͖�35���l�Ɍ������A�ߘa42�N�ɂ̓s�[�N���̖��Ɍ������邱�Ƃ��\������Ă��܂��B�n���Í\�z�ɂ����āA�a�̎R��Ì��͕a���ߏ�n��Ƃ���Ă���A�ߘa6�N�����ɍ���Ґl���������ɓ]���A��ÁE���Ƃ��Ɏ��v���ቺ���邱�Ƃ������܂�Ă��܂��B�����āA�a�̎R�s�͑��ւ̒ʋE�ʊw�����Ƃ������Ƃ�����A�l�ފm�ۂ����Ɍ������A���҂̌����Ɠ�����̊m�ۂƂ������ɑ��A�n��̃j�[�Y�ɏ_��ɑΉ��ł���g�D�����邱�Ƃ��o�c�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��v�i�ȉ��u �v���͉F�s�{���̐����j�B
�@���@�́A5�L�������̐g�̕s����ړ���i���Ȃ����҂̖������}�����{���Ă���B���̖������}�����p���A�n��j�[�Y�̕������������Ƃ���A2���������X�[�p�[�}�[�P�b�g�̑������X��H���o�X�̔p���\���ɂ��A��������E��ʓ���������Ă��邱�ƁA�𗬋@��̌����A���N���ȂǂłЂ�������̍���҂��������Ă���Ȃǂ̒n��ۑ肪��������ƂȂ����B
|
|
|
| ���@�F�s�{�a�@�̑�����t�ƃ��n�r���� |
�n��R�~���j�e�B�̋��_�u�Ȃ�R�~�v���J��
�@�����̒n��ۑ�ɑ��A��������a�@�ɑ����^��ł��炢�A�C�y�Ɏ�f�⑊�k�����Ă��炦�邱�Ƃ�ڎw���A����27�N10���ɒn��̑�����𗬋��_�Ƃ��Č��N�ƃR�~���j�e�B���x������u�Ȃ�R�~�v���J�݂����B
�@�Ȃ��A�u�Ȃ�R�~�v�Ƃ����{�ݖ��́A�u�a�̎R�s�_�ɂ���R�~���j�e�B�v�̗��̂ŁA�n��Z������̓I�ɏW�܂�A���܂��܂Ȋ�����𗬂�ʂ��Č��N�ɂȂ��鋏�ꏊ�Ƃ��ĉ^�c���Ă���B
�@�a�@�~�n���̊Ō�t�������đւ����u�Ȃ�R�~�v��2�K���ĂŁA1�K�ɂ͑��ړI�X�y�[�X��L�b�Y���[���A���k���Ȃǂ�ݒu���A2�K�ɂ͐E���H����x�e��������A�ЊQ���̔��ꏊ�Ƃ��Ă̋@�\������Ă���B
�@�u�Ȃ�R�~�v�̎�Ȋ����Ƃ��ẮA�@�O���H���ł̘a�̎R��V�����`�̒A�A�@�l�X�^�b�t��{�����e�B�A�u�t�ɂ��e�틳����u���̊J�ÁA�B���E�ɂ���ÁE���E�����Ɋւ��鑊�k�A�C�_�q�ǂ��H���̊J�ÁA�D�s���̌��^�_���̉^�c�Ȃǂ��s���Ă���B
�@�O���H���Œ����V�����`�i�T�ւ�胉���`1,200�~�j�́A�a�̎R�̐V�N�ȐH�ނ��ӂ�Ɏg�p���A�n��Z������́u���N�ɂ悢�����łȂ��A���������v�ƍD�]�ő����̗��p������B�����K���a�\�h���f�̎�f�҂ɂ͖�V�����`�����Ă���Ƃ����B
�@�u��V�����`��������R�Ƃ��ẮA�����̕����W���{�݂ɂ��邽�߂̃c�[�����ق����ƍl�����Ƃ��ɁA�w�����������N�ɂ悢���́x�Ɓw�y�������Ɓx��g�݂��킹�邱�ƂŐl���W�܂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B��V�����`�̕���9��ނ��炢����A�r���b�t�F�`���Ŋy���݂Ȃ���A�̒��ɉ��������N�ɂ悢�H�����Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����A��b�̂��������ɂȂ�R�~���j�P�[�V�����c�[���ƂȂ��Ă��܂��v�B
�@�O���H���̗��p�҂ɂ͑̎��`�F�b�N�V�[�g���L�����Ă��炢�A�`�F�b�N���ڂ̑��������̎���̒��ɉ����āA�{���@�₨�����ߐH�ނ��L�ڂ����J�[�h��n���A����I�ԂƂ��̎Q�l�ɂ��Ă�����Ă���Ƃ����B
|
|
|
| ���@�a�@�~�n���ɕ��݂���u�Ȃ�R�~�v�̊O�� | |
|
|
|
| ���@�O���H���Œ���u�a�̎R��V�����`�v�B���̓r���b�t�F�`���ŁA�y���݂Ȃ���A�����������N�ɂ悢�H�����Ƃ邱�Ƃ��ł��� | |
���N�E��E�����Ɋւ��鑽�l�ȃv���O���������{
�@���ړI�X�y�[�X�ł́A���N�������E�����Ɋւ���u���A����Ȃǂ̃v���O���������{���Ă���B�J�ݓ�������J�Â���u�Ȃ�R�~�̑��v�i�T2��j�́A�����ɂȂ�l�C�v���O�����ƂȂ��Ă���B
�@���N���Ɋւ���v���O�����ł́A���K�A�t���_���X�A�E�N�����A�s���|���A�����A���N�����Ȃǂ�����A�����ɖ𗧂v���O�����Ƃ��ẮA�X�}�z�A���O�����A�����J�^�����A�����Ɋւ���Z�~�i�[�Ȃǂ����{�B����ɁA�e�q��ΏۂƂ����x�r�[�}�b�T�[�W�A���g�~�b�N�A�e�q�p��b�ȂǁA���ǂ����獂��҂�Ώۂɂ������l�ȃv���O�����𑵂��Ă���B
�@���̂ق��ɂ��A�F�m�ǃJ�t�F�₪��T���������I�ɊJ�Â���ق��A�n��̈�Ë@�ցE���{�݂̃X�^�b�t��Ώۂɂ�������u��ÂƉ��̖����m�v���J�Â��A��L�ƂƂ��ɘA�g�̐��̋�����}���Ă���B
�@�����J�Â���u�_�q�ǂ��H���v�́A���ǂ����獂��҂܂Ŗ���100�l���闘�p������A������𗬂̏�ƂȂ��Ă����B�R���i�ЂŊ������x�~�����ۂɂ́A����360�H�ٓ̕��z�z���s���ƂƂ��ɁA���݂��H���z�z���ƂɎ��g��ł���B
�@���݂����ÁE���E�������k���ł́A�a�@�̒n��A�g�����u�Ȃ�R�~�v�Ɉڐ݂������Ƃɂ��A�풓����Љ���m�A���_�ی������m�A�Ō�t�A�P�A�}�l�W���[�Ȃǂ̐��E�ɖ����ő��k�ł���̐��������Ă���B
|
|
 |
| ���@�u�Ȃ�R�~�̑��v�i�T2��j�́A�����ɂȂ�l�C�v���O���� | ���@�����ɖ𗧂��p���@���w�ԃX�}�z�����̗l�q�B���̂ق��ɂ��p��A���K�A�t���_���X�A�����A���N�����A���O���������ȂǑ��l�ȃv���O���������{ |
|
|
 |
| ���@�����J�Â���u�_�q�ǂ��H���v�ɂ́A���ǂ����獂��҂܂ő����オ�W�܂��Ă����B�i�R���i�Јȍ~���݂ł͖���360�H�ٓ̕��z�z���s���Ă���j | ���@�ݒu�����ÁE���E�������k���ł́A���E�ɂ�閳�����k���s�� |
�n��Z������̓I�Ɋ����ɎQ��
�@�u�w�Ȃ�R�~�x�̊����́A�t�B�������h�̋���w�҂�����m�b�g���[�L���O�Ƃ����h���іڂÂ���g�̊��������b�g�[�ɂ��Ă��܂��B�ɂ����іڂ������������A�n��̉ۑ����������Ƃ��ɋ������іڂɂ�����̂ł��B�ɂ����іڂ́A������݂��Ȃ��A�S�n�悭�K�v�ȂƂ��ɕK�v�Ȑl�ƌ��т����悢�Ƃ����Ƃ���ŁA���܂��܂ȉۑ�������ł���ƍl���Ă��܂��B�܂��A�w�Ȃ�R�~�x�̓��F�Ƃ��āA�e��v���O�����̎Q�����500�~������Ƃ��邱�ƁA������@���F�������������֎~����ȊO�͗��p�K�Ȃ��A���p�҂����Ă��������������������邱�Ƃ���{�Ƃ��Ă��܂��B���݁A�{�����e�B�A�u�t�����ł�30�l����o�^������A�����̊��E�^�c���قڂ��C�����邱�Ƃɂ��A�n��Z�������������̋��ꏊ���Ǝv���āA��̓I�Ɋ������Ă����������ƂɂȂ����Ă��܂��v�B
�@�ɂ����т������邱�Ƃ◘�p�K���Ȃ����Ƃ́A���p�҂����������o�[�ɌŒ肳����Ԃ�h���A���ʂ��̂悢���ꏊ���^�c���邱�Ƃ��ł���v���ƂȂ��Ă���Ƃ����B
�@����ɁA�n��Z���Ɏ��������̋��ꏊ���Ɗ����Ă��炦��悤�A�n��̊W�҂������ƂȂ�A����30�N�ɂm�o�n�@�l�����Ċ������s���Ă���A�ߘa3�N�ɂ͔F��m�o�n�@�l�̔F���Ă���B
�@�ߘa6�N�x�ɂ́A�n��R�~���j�e�B�̊�����ʂ��Ďs���̌��N���i�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��]������A�a�̎R���m���\������܂��Ă���B
���p�Ґ��͌�2900�l�ɒB���A�n��ɐZ��
�@���݁A�u�Ȃ�R�~�v�̌��ԗ��p�Ґ��͉���2,900�l�ɂ̂ڂ�A���܂��܂Ȋ�����𗬁A���k�̏�Ƃ��Ēn��ɍL���Z�����Ă���B
�@�u�����̐l�������W�܂�v���Ƃ��ẮA�n��Z���ƈꏏ�Ɏ��������̋��ꏊ�����肠���Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B�錍�Ƃ��Ă͎����������܂�o�����Ȃ����ƂŁA�n��Z������̓I�ɂȂ�A�������L�����Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��v
�@�u�Ȃ�R�~�v�̉^�c�����̊m�ۍ�Ƃ��ẮA��V�A���o�T�_�[�{���u�������{���A�Ǝ��ɍ쐬�������ޔ�Ǝ�u���Ȃǂ��^�c�����ɏ[�ĂĂ���B��V�A���o�T�_�[�{���u���́Ae-���[�j���O�ŔF�莑�i���擾�ł���d�g�݂�����A����܂łɑS������200�l�ȏオ��u���Ă���Ƃ����B
�@���̂ق��ɂ��A�a�̎R���̓��Y�i�ł��鉷�B�݂���̔�ƎR�����u�����h������V�֗̕��|�u�O���}���|�v�����i�����A�̔����Ă���B
|
|
| ���@1�K�̑��ړI�X�y�[�X�ł́A�O���H���⌒�N�E�����E��Ɋւ��鋳���ȂǁA���܂��܃v���O�������J�ÁB���ԗ��p�Ґ��͉���2,900�l�ɂ̂ڂ� |
�u�Ȃ�R�~�v�̉^�c�����ݏo������
�@�u�Ȃ�R�~�v�̍̎Z���ɂ��ẮA�v���O�����̎Q�����1��100�`500�~���x�ŁA�����̌��z��ɂ͂��܂�A�ێ���A�l���������A�P�̂ł͎��v�ݏo���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ŁA�@�l�S�̂̎��v�ɑ傫���v�����Ă���Ƃ����B
�@�a�@�o�c�ւ̌��ʂƂ��ẮA�u�Ȃ�R�~�v�ɑ����̐e�q���Q�����邱�Ƃɔ����A�\�h�ڎ팏�����啝�ɑ������Ă���B�Ƃ��ɐ����K���a�\�h���f��l�ԃh�b�N�Ȃǂ̌��f���Ƃ̎�f�҂́A�u�Ȃ�R�~�v�̊J�ݑO�ɔ��3�{�ɑ������Ă���Ƃ����B
�@����ɁA�Љ�v�������Ɏ��g�ނ��Ƃɂ��A�n��̈�Ë@�ւ��쎖�Ə�����a�@�̒m���x�ƐM���������܂�A�Љ�҂���������ƂƂ��ɑމ@�������X���[�Y�ɍs����悤�ɂȂ�A�a���̉ғ����A��]���Ƃ��ɏ㏸���Ă���B
�@�u�w�Ȃ�R�~�x�����ݏo���Ă�����ʂƂ��ẮA���҂̑�����a���̉ғ����̏㏸�ɂ���Ǝ��v�ɂƂǂ܂炸�A�Љ�v�������Ɏ��g�ޕa�@�œ��������Ƃ������E�̉��傪�����A�̗p�����ɗ͂����Ȃ��Ă��l�ނ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B�Љ�v�������Ɍg���E���́A��肪����B�����������邱�ƂŒ蒅�������܂�A�n��̃j�[�Y�ɑ��ď_��ɑΉ��ł���l�ނ̈琬�ɂ��Ȃ����Ă��܂��v�B
�@�n��Z���Ƃ̐M���W�̍\�z��n��̈�Ë@�ցE��쎖�Ǝ҂Ƃ̘A�g�̐�����������A���@���o�c�ۑ�ɂ�����n��j�[�Y�ɏ_��ɑΉ�����g�D�Â���ɁA�n��R�~���j�e�B�������傫�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ�����������B
�@�n��R�~���j�e�B�̋��_������A�n��̊������ƂƂ��ɕa�@�o�c�ւ̌��ʂݏo���Ă��铯�@�̍���̎��g�݂����ڂ����B
�@
��Ö@�l�v�m�� �F�s�{�a�@�@��������
�F��NPO�@�l ���N�ƃR�~���j�e�B���x������@�Ȃ�R�~�@��\����������
�F�s�{ �z�q�@��
 �@����̓W�]�Ƃ��ẮA�a�@�̌��đւ����v�悵�Ă���A�ߘa8�N5���ɐV�a�@���I�[�v������\��ƂȂ��Ă��܂��B�V�a�@�̐v�ɂ��Ēn��Z���ƈӌ��������s���A�v�]�̂����������̃X�y�[�X��n���C�A���K�[�f��������\��ł��B
�@����̓W�]�Ƃ��ẮA�a�@�̌��đւ����v�悵�Ă���A�ߘa8�N5���ɐV�a�@���I�[�v������\��ƂȂ��Ă��܂��B�V�a�@�̐v�ɂ��Ēn��Z���ƈӌ��������s���A�v�]�̂����������̃X�y�[�X��n���C�A���K�[�f��������\��ł��B�@���݁A�u�Ȃ�R�~�v�ɂ͋C�y�ɗ������������������܂����A��f���Ȃ��Ă������𗘗p������A�a�@�S�̂��R�~���j�P�[�V�����̏�Ǝv���Ă��炦��悤�ȁA�n��ɊJ���ꂽ�a�@��ڎw���Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@�܂��A�u�Ȃ�R�~�v�ɂ��ẮA�L�b�Y���[���ňꎞ�ۈ�����{������A���ǂ������̊w�K�x������ی�̋��ꏊ�Ƃ��ĊJ�����邱�Ƃ��\�z���Ă��܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| �a�@�J�� | ���a45�N | ||
| �������^�a�@�� | �F�s�{ �@�v | ||
| �a���� | 80���i��××{44���A�n���P�A36���j | ||
| �f�É� | ���ȁA�ċz��ȁA�z��ȁA������ȁA���`�O�ȁA���ȁA�����ȁA���ː��ȁA���e�畆�ȁA�`���O�� | ||
| �Z�� | ��640�|8303 �a�̎R���a�̎R�s�_505�|4 | ||
| TEL | 073�|471�|1111 | FAX | 073�|473�|8567 |
| URL | https://www.utsunomiya-hospital.com/ | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2025�N2�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B


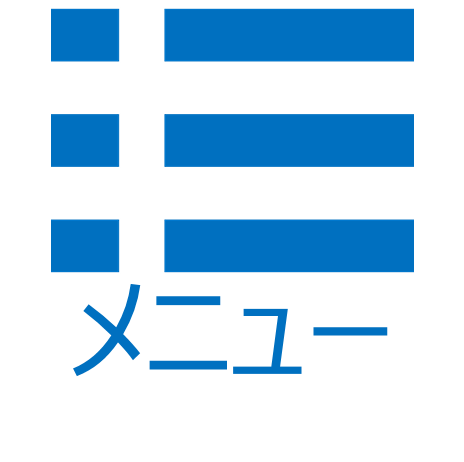

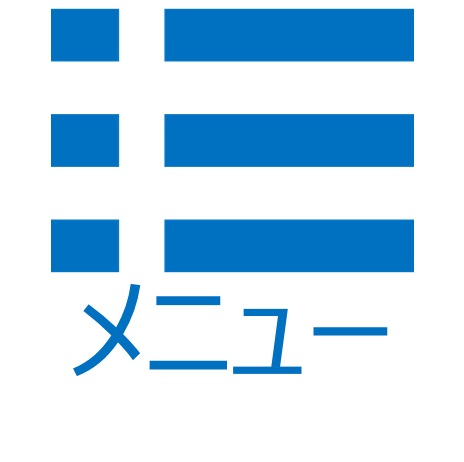
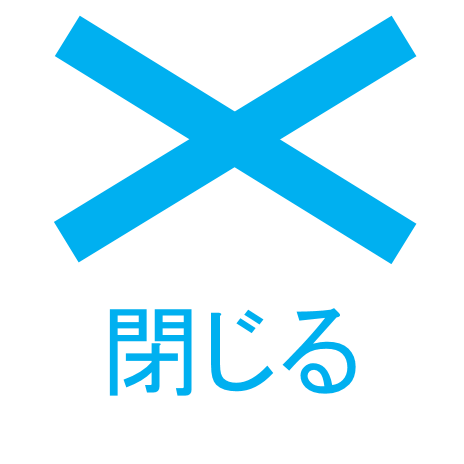
 WAM NET�����p�K�C�h
WAM NET�����p�K�C�h
