|
|
| ▲ 施設の外観 |
地域ニーズに応えた福祉事業を展開
栃木県にある社会福祉法人同愛会(法人本部:栃木県塩谷郡)は、人と人との関わりを福祉の原点とし、障害の種別・年齢・信条などにとらわれずに個別的な価値観とライフスタイルに応じた支援に取り組んでいる。
同法人の沿革は、昭和7年に東京都において、傷痍軍人や母子寡婦などの保護施設を運営する社団法人大日本傷痍軍人同人會を設立したことに始まる。その後、社会福祉法人同愛会に組織変更を行い、平成7年に法人本部を栃木県に移転し、障害福祉事業を中心に高齢者福祉、保育事業を展開している。
現在の法人施設は、障害福祉事業では障害者入所施設、グループホーム、生活介護、日中一時支援、就労継続支援B型事業など、高齢者福祉事業では地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム、小規模多機能型居宅介護、デイサービスセンター、保育事業では認可保育所、学童保育を運営。姉妹法人となる社会福祉法人あいのかわ福祉会と一体的に事業を運営している。
同法人がこれまで地域で担ってきた役割について、理事長の菊地月香氏は次のように説明する。
「当法人は、人と人とのつながりを大切にしながら、地域生活での困りごとはすべて福祉課題として捉え、サポートしていくことを使命としてきました。地域ニーズや利用者、行政などの要望に応えるかたちで、こどもから高齢に至るまでの切れ目のない支援体制を整備し、家族を含めた包括的なサポートを行っています。また、平成29年の社会福祉法人制度改革で、公益的な取り組みが義務化される以前から、利用者の社会参加を含め、社会貢献活動に積極的に取り組んでいます」。
 |
 |
| ▲ 「なかが和苑」の受付・ロビー | ▲ 生活介護で創作活動に取り組む利用者の様子 |
地域の福祉拠点「なかが和苑」を開設
同法人は、令和2年5月に那須郡那珂川町において、地域福祉の拠点となる複合施設「なかが和苑」を開設した。
同施設は、バリアフリー温泉宿と、障害福祉事業所の生活介護、短期入所、日中一時支援、就労継続支援B型事業、相談支援事業所、高齢者福祉事業の通所介護事業所を併設し、障害の有無や世代を超えたつながりを生む、地域共生の拠点となっている。
「『なかが和苑』を開設した経緯については、那珂川町では高齢者の通所介護事業を運営していましたが、障害福祉サービスが整備されておらず、障害者とその家族から、自分の慣れ親しんだ地域でサービスを受けたいという声がありました。開設地については、県が運営していた障害者の保養施設の経営が立ち行かなくなり、プロポーザルを経て譲渡売却というかたちで譲り受けました。当初は、障害福祉事業所をメインに考えていましたが、障害者やその家族、当事者団体から障害者の宿泊機能を残してほしいという要望があったことや、障害者の就労支援や職員の多様な働き方につながり、地域住民と利用者がふれあう場になるのではないかと考え、温泉施設と障害福祉事業所を融合させた複合施設を開設しました」(菊地理事長)。
 |
| ▲ 温泉宿の客室は、1〜4人室まで多様なタイプの部屋を用意。短期入所の居室もほぼ同様の広さがあり、快適な生活環境を提供している |
高齢者・障害者にとどまらず多くの地域住民が利用
「なかが和苑」の建物は2階建てで、館内は客室を含め、すべてバリアフリーとなっている。1階にある温泉は、いずれの浴室もスロープ付きで、車いすで入浴できる大浴場やストレッチャー付きの浴室、プライバシーに配慮した貸し切りの浴室(家族風呂)を備えている。
「日帰り温泉の入浴料は大人350円、那珂川町民は250円で利用することができます。もともと、温泉施設として地域に浸透していたため、日帰り温泉は地域の高齢者や障害者にとどまらず、多くの地域住民に利用いただいています。隣接する茨城や東京からの宿泊客も多く、特別支援学校や福祉施設の旅行で利用されることも多くなっています」(菊地理事長)。
障害福祉サービスについては、生活介護、短期入所、日中一時支援、就労継続支援B型、相談支援事業所を併設するほか、令和6年には敷地内に障害者グループホームを新設し、障害児者の生活支援、就労支援、居住支援を包括的にサポートする体制を整備した。
就労継続支援B型事業では、施設全体の清掃や客室のベッドメイキングのほか、敷地内にある畑で農作業などの業務に取り組んでいる。
就労支援の方針について、業務執行理事の伊藤淳一氏は次のように説明する。
「就労継続支援B型事業は、いかに工賃を上げるかというところに重きを置く事業所が多くなっていますが、そうすると、働く意欲があるにもかかわらず、そこからこぼれてしまう人が出てきてしまいます。当法人の就労支援では、工賃を上げることを目指すというより、楽しくやりがいをもって働けることを重視し、一人ひとりのペースで働くことのできる環境づくりに力を入れています」。
また、短期入所の居室は、温泉宿の客室とほぼ同様の広さがあり、施設周辺が豊かな自然に囲まれている生活環境は利用者・家族からも好評で、県外からの利用者も多くなっている。障害者の短期入所は、新たな場所へ家族を預けることに不安を感じる保護者が少なくないが、初回の利用時に保護者も宿泊客として利用して、施設の雰囲気を感じてもらうことで継続的な利用につながるケースもあるという。
|
|
 |
| ▲ 複数ある浴室はいずれもスロープ付きで、プライバシーに配慮した貸し切りの浴室(家族風呂)も備える | |
|
|
|
| ▲ 就労継続支援B型事業では、温泉宿の清掃や客室のベッドメイク、農作業などの業務に取り組む。温泉施設の利用客とふれあう機会も多い | |
世代を超えた交流やつながりが生まれる
利用者同士や地域住民の交流について、「なかが和苑」管理者・サービス管理責任者の塚田翔伍氏は次のように説明する。
「当施設では、障害と高齢サービスの利用者同士が日頃から交流を図り、高齢者が障害者の面倒をみてくれることも日常的な光景となっています。利用者が一般のお客さんとふれあう場面も多くあります。日中一時支援や短期入所では、こどもから成人まで利用しているため、世代を超えたつながりも生まれています。今後、求められる地域共生社会が言葉だけでなく、実際に実現できる場だと思っています」。
さらに、令和3年6月に敷地内にバイクカフェの「BATOWL Cafe」をオープンし、店内には菊地理事長の家族が知人から譲り受けた往年のバイクメーカー「目黒製作所」の車両を複数展示している。
「バイクカフェとした理由は、コロナ禍でバイクブームとなっていたことや、このあたりはツーリングの人気スポットとして全国から多くのライダーが訪れる地域ということがあります。バイク鑑賞を目的に遠方から訪れる方も多く、那珂川町のことを知ってもらうことで、地域の観光拠点になることや関係人口が増えるきっかけになればと思っています」(菊地理事長)。
また、店内で提供するメニューは就労支援で利用者が栽培した野菜を用いており、社会とのつながりを実感できる場にもなっている。
|
|
|
| ▲ 左から「なかが和苑」管理者・サービス管理責任者の塚田翔伍氏、業務執行理事の伊藤淳一氏 | ▲ 施設内では障害と高齢サービスの利用者同士が日常的に交流している |
|
|
 |
| ▲ 敷地内にオープンしたバイクカフェ「BATOWL Cafe」 | |
地域生活支援拠点としての取り組み
地域における福祉拠点の役割としては、同施設は障害児者の生活を支える機能や体制を整備することにより、那珂川町の地域生活支援拠点として位置づけられている。
「那珂川町の場合、『重層的支援体制整備事業』の準備事業と絡めて、地域生活支援拠点を実施しているところがあります。当施設は障害者の相談支援を実施していますが、『重層的支援体制整備事業』の相談支援もあわせて行うことで、地域で困っている人のなかで福祉サービスが必要な場合は、切れ目なくつなぐことができ、さまざまな人たちの就労体験や宿泊体験などを行うことも可能となっています。ひきこもりの若者を受け入れ、当施設の利用者と一緒に就労体験の機会を提供することにより、一般就労に結びついたケースもあります。短期入所を活用して虐待などの緊急時の受け入れにも対応しています」(菊地理事長)。
法人全体の取り組みとしては、宇都宮市でこども食堂や自立準備ホーム、生活困窮者就労訓練事業など、多岐にわたる活動を行っている。
「公益的な取り組みを進めるメリットとしては、社会貢献にとどまらず、法人・施設に協力してくれる人たちが増えるということがあります。例えば、障害分野の居住系の施設は、地域連携推進会議を設置しなくてはなりませんが、地域の関係者を集めやすく、制度にも対応しやすくなります。さらに、いまの若者は社会貢献活動への関心が高く、地域に開かれた施設で働きたいと入職を希望することも増えており、人材確保にもつながると感じています」(伊藤氏)。
公益的な取り組みを通じた新たな事業を創出
今後の展望としては、地域ニーズにあわせた事業展開を行うとともに、次世代を担う管理者を育成していく必要性をあげている。
「近年、社会福祉事業は運営自体が大変厳しい時代に入っています。とくに、当法人の場合、法人本部のある塩谷町をはじめ、事業所を運営する那珂川町や益子町などの5町が消滅可能性自治体としてあげられており、利用者とともに働き手が急激に減少していくことが大きな課題となっています。今後は、地域ニーズにあわせて施設・事業所のダウンサイジングや、採算はとれないものの地域に必要な事業を比較的安定した事業でカバーしていく必要がありますし、公益的な取り組みを通じて、新たに必要とされる事業展開を考えていかなくてはならないと思います。多様化している福祉課題に対応していくためにも、総合力や人間力を備えた次世代を担う管理職の育成が急務だと考えています」(菊地理事長)。
地域の困りごとを福祉課題として捉え、サポートしていく同法人の今後の取り組みが注目される。
社会福祉法人同愛会
理事長 菊地 月香氏
 ティネットとして地域課題や困りごとを把握し、サポートしていくことが大きな役割となりますが、そのようなアンテナの感度を高めながら、多角的にものごとを捉えていくことが大切だと思います。
ティネットとして地域課題や困りごとを把握し、サポートしていくことが大きな役割となりますが、そのようなアンテナの感度を高めながら、多角的にものごとを捉えていくことが大切だと思います。また、「なかが和苑」を開設して思ったことは、福祉だけでなく、地域のさまざまな資源に着目し、福祉とうまく結びつけていくことにより、衰退していくかもしれない産業を守ることができるのではないかということです。過疎化が進む地域のなかで、このような地域の活性化にも取り組んでいきたいと考えています。
<< 施設概要 >>
| 病院開設 | 令和2年5月 | ||
| 併設施設 | 生活介護、日中一時支援、短期入所、就労継続支援B型、地域密着型通所介護、相談支援事業所、バリアフリー温泉宿 | ||
| 法人施設 | 【障害福祉】障害者入所施設、短期入所、障害者グループホーム、生活介護、日中一時支援、就労継続支援B型、相談支援事業 【高齢者福祉】地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所、認知症対応型グループホーム、小規模多機能型居宅介護、デイサービスセンター 【保育】認可保育所、学童保育 |
||
| 住所 | 〒324-0618 栃木県那須郡那珂川町小口1728 | ||
| TEL | 0287−92−5511 | FAX | 0287−92−5513 |
| URL | http://three-ai.jp/ | ||
■ この記事は月刊誌「WAM」2025年5月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。
月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。


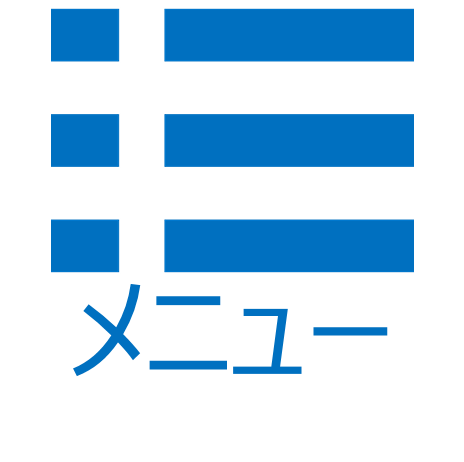

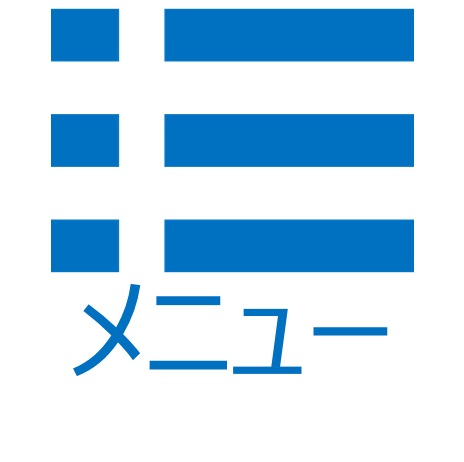
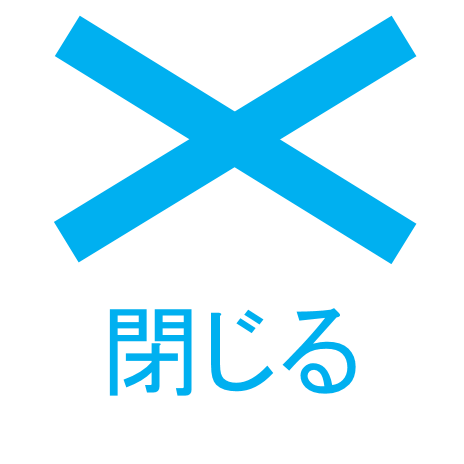
 WAM NETご利用ガイド
WAM NETご利用ガイド
