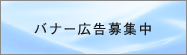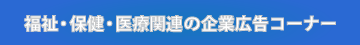�T�[�r�X��g�ݎ���Љ�
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
| ���@�{�݂̊O�� |
�n��ɍ����������T�[�r�X���
�@�x�R�s�ɂ���Љ���@�l��������̕�����́A�u�������́A�F���܂����S���čK���Ȑ������A�Z�݊��ꂽ�n��ʼnc��ł����������߂ɍv�����Ă����܂��v�Ƃ����@�l���O�̂��ƁA�n��ɍ����������T�[�r�X����Ă���B
�@���@�l�̐ݗ��o�܂́A����5�N�Ɂu����n�敟���v��v�����肳�ꂽ�����A�n��ɂ͓��ʗ{��V�l�z�[����1�J�����Ȃ��A�����̗v���ɂ��n���J�ƈオ���S�ƂȂ�A����10�N�ɎЉ���@�l��ݗ����A���ʗ{��V�l�z�[�������É����J�݂������ƂɎn�܂�B
�@���̌�A�f�C�T�[�r�X�Z���^�[�A������x�����Ə��A�n���x���Z���^�[�Ȃǂ��^�c���A����29�N�ɂ͕x�R�s�̌��厖�Ƃ̍̑����A�n�斧���^���ʗ{��V�l�z�[�������É����������J�݂��Ă���B
�@����ɁA���@�l�͗ߘa6�N4���ɒn��̈�Ö@�l���^�c������V�l�ی��{�݁A�O���[�v�z�[���A���K�͑��@�\�^������A�f�C�T�[�r�X�Z���^�[�̎��Ə��n���A���ƋK�͂��g�傳����ƂƂ��ɁA���݂̖@�l���i���@�l���F�钷�N�v��j�ɉ��̂��Ă���B
�@���Ə��n�̌o�܂ɂ��āA�������̊��L�s���͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u���Ə��n���s������Ö@�l�́A���@�l�Ɠ��l�ɑ���n��ň�ÁE��쎖�Ƃ�W�J���Ă��܂������A�ߘa5�N6���Ɂw�^�c�����쎖�Ə�4�J��������Ăق����x�Ƃ����\���o������A�n��̗��p�҂̐�������邽�߂Ɏ���܂����B���Ə��n�ɔ����A���Ə�����7���Ə�����11���Ə��A�E������130�l����250�l�Ɋg�債�Ă��܂��B�܂��A�@�l����ύX�������R�Ƃ��ẮA�n��ɂ������쎖�Ƃ�����Ƃ����Ӗ��Œn�於������ƂƂ��ɁA���Ə��n�����@�l�E���◘�p�҂̃}�C�i�X�C���[�W�@�������Ƃ����z��������܂����v�i�ȉ��u �v���͊�䗝�����̐����j�B
�ȃG�l���̍����{�݂Ƃ��Č��M��6�����팸
�@����29�N�ɊJ�݂����n�斧���^���{�u�����É��������v�̓��������29�l�ŁA�S�����̃��j�b�g�^���{�ƂȂ��Ă���B�����͏ȃG�l���M�[���̍�����i�I�Ȏ{�݂Ƃ��āA����28�N�x�Ɍo�ώY�ƏȂ�ZEB���؎��Ƃō̑�����Ă���B
�@�y�d�a�́ANet Zero EnergyBuilding�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���f�B���O�j�̗��̂ŁA���z�����d�⎩�R�G�l���M�[���p�A���f�M�A���������C���s���ݔ��A�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���ȂǁA�ȃG�l���M�[�Z�p�ƍĐ��\�G�l���M�[��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�����ŏ����N�Ԃ̃G�l���M�[�������ނ˃[���ɂ��邱�Ƃ�ڎw�����������w���Ă���B
�@�y�d�a���؎��Ƃ̍̑�����ƁA�ȃG�l���M�[�Ɋւ���ݔ����3����2��⏕���Ƃ��Ď邱�Ƃ��ł��A���{�݂͍Ő�[�̏ȃG�l���M�[�Z�p�̊��p�ɂ��A�{�ݑS�̂̌��M��͈�ʓI�ȕ����{�݂Ɣ�r���Ė�6���̍팸���������Ă���Ƃ����B
 |
|
| �����@�e���j�b�g�ɐݒu�������Ƌ��L�X�y�[�X | ���@�����É��������̎�t�B�n���x���Z���^�[�A������x�����Ə��̑����� |
|
|
|
| ���@�Ő�[�̏ȃG�l���M�[�Z�p�̊��p�ɂ��A���M��͈�ʓI�ȕ����{�݂Ɣ�r���Ė�6 ���̍팸���������Ă��� |
���p�ҁE�X�^�b�t�ɑI��閣�͂���E��Â���Ɏ��g��
�@����ɁA���{�݂ł͂h�b�s�E��샍�{�b�g��ϋɓI�ɓ������邱�Ƃɂ��A���p�҂̃P�A�̎�����ƂƂ��ɁA�X�^�b�t�̒蒅���i�Ɏ��g��ł���B
�@�u�h�b�s�E��샍�{�b�g���������������Ƃ��ẮA���{�݂͎R�ԕ��ɗ��n���Ă��邱�Ƃ�����A�J�ݎ��ɃX�^�b�t���W���Ă��l���W�܂�Ȃ��Ƃ����o�������܂����B��쌻��Ől�ޕs��������������Ȃ��A���p�҂����łȂ��A�A�E��]�҂���I��閣�͂���E������邱�Ƃ�ڎw���A�@�����@��E��샍�{�b�g���p�ɂ�鍘�ɗ\�h��A�A�c�w�E�h�b�s���i�ɂ�錻��̐��Y������A�B�@�l�u�����h�A�b�v�̂��߂̃`�������W�A�C�ϋɓI�ȊO���ւ̏�M��4����j�Ɍf���A���{�݂Ƃ̍��ʉ���}���Ă��܂��v�B
�@�h�b�s�E��샍�{�b�g�̓����̗���Ƃ��ẮA�ߘa2�N�x�̎��ƌv���5�r�i�����A���ځA���|�A�����A�K���j�̐��i�ƁA3�l�i�����A���_�A�����j�̍팸��ł��o���A1�N�Ԃ̊����̂Ȃ��ŃX�^�b�t�S���ʼn�쌻��̉ۑ�𒊏o�B�ߘa3�N4���Ɂu�h�b�s���i�ψ���v��ݒu���A�s�v�ȋƖ����팸����ƂƂ��ɁA�h�b�s�E��샍�{�b�g�̓����ɂ��P�A�̎��̌���ƋƖ��̌������Ɏ��g�B
���L�^�ɗv���鎞�Ԃ��啝�ɒZ�k
�@���Ɩ��̐��Y������ł́A���`���C���J���≹���ʼn��L�^�����͂ł���uCareWiz �n�i�X�g�v�i������ЃG�N�T�E�B�U�[�Y�j�A���\�t�g�́uCAREKARTE�i�P�A�J���e�j�v�i������ЃP�A�R�l�N�g�W���p���j�����Ă���B
�@���`���C���J���́A�����E���Ԃł̓����ʘb��^���@�\������A�u�n�i�X�g�v�Ɓu�P�A�J���e�v�ƘA�����邱�Ƃɂ��A���p�҂̌�����P�A���s���Ȃ���A�������͂ʼn��L�^���쐬���邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B
�@�����ƕ����ŋL�^���c�邽�߁A�\������Ƃ��Ă����p���邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
�@�u���`���C���J���Ɖ������̓V�X�e�����������ʂƂ��āA�W���Ζ����ԓ�����̉��L�^�ɗv�������Ԃ������O��33������17���ɑ啝�ɒZ�k���܂����B���̈���ŁA�L�^�������ʂ�2�{�ƂȂ�A�������ƋL�^�̏[�����ɂ��P�A�̎������߂邱�ƂɂȂ����Ă��܂��B���̋@������Ă������낢�Ǝv�����̂́A��ʓI�ɂh�b�s�����ɒ�R��������N�z�X�^�b�t�������Ȃ��A�p�\�R���̃L�[�{�[�h���͂����S�ɂȂ��Ă���50�`60�Α�̃X�^�b�t�����i���ɂȂ��Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�O���l���l�ނ������Ă���Ȃ��A�O���l�̑����{�݂قlj������͂͗L�����Ɗ����Ă��܂��v�B
�@���̂ق��ɂ��A���܂��܂ȃA�v���P�[�V�����ō쐬���ꂽ�f�[�^�A�e�`�w�A�X�L�����������ꌳ���Ǘ�����uDocuWorks�i�h�L�����[�N�X�j�v�i�x�m�t�C�����r�W�l�X�C�m�x�[�V�����j��Ζ��\�쐬�\�t�g�����A�Ɩ��̌�������y�[�p�[���X���������B�����@�Ŏg�p����o�͗p���͌�3,500���A�e�`�w����M�p���͌�795���̍팸�ɂȂ����Ă���Ƃ����B
 |
|
| �����@�E���̍��ɗ\�h��Ƃ��Ĉړ����X�^���f�B���O���t�g�i�ʐ^��j�A�ڏ�T�|�[�g���{�b�g�uHug�v�i�ʐ^���j�� | ���@���`���C���J�����g�p���A�������͂ʼn��L�^���쐬����l�q�B�Ɩ��̌������ɂ�藘�p�҂ւ̒��ډ�ɏ[�Ă鎞�Ԃ����� |
|
|
 |
| ���@�Ζ��\�쐬�\�t�g�̓����ɂ��A�쐬���Ԃ��啝�ɍ팸����ƂƂ��ɁA�E���͊e���̃X�}�z�Ŋm�F�ł��邽�߁A�y�[�p�[���X���ɂ��Ȃ����Ă��� |
�h�b�s�����p���������K���̉��P
�@�h�b�s�����p�����P�A�̎��g�݂ł́A�����҂̐�����Ԃ�c�����A�������Y�����P�ɂȂ���A�����x���V�X�e���u����r�b�`�m�v�i�p���}�E���g�x�b�h������Ёj�����Ă���B
�@�u����r�b�`�m�v�́A�}�b�g���X�̉��ɐݒu�����Z���T�[�ɂ��A�������̌ċz�A�S���A�Q�Ԃ�Ȃǂ𑪒肵�A������Ԃ̃f�[�^�����A���^�C���Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��A�f�[�^�͂��邱�ƂŎ��̍��������̒�����҂̐����K���̉��P�ɂȂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B
�@�u�w����r�b�`�m�x�����p�����x������Ƃ��āA����j�������ҁi92�A�v���5�j�́A����t�]�̌X��������A�P���̐������Ԃ͕���1����59���A��Ԃ̒��r�o����6���Ԉȏ�A15��ȏオ��Ë@�֎�f�̖ڈ��ƂȂ�������̓��w����241��Ƒ����ł����B�����҂̐����K�������P���邽�߁A�X�^�b�t��2�J���Ԃ����āA�����̗����𑣂��ƂƂ��ɁA���{�l�̋C���ɂ��킹���������s���A�������Ԃ𑝂₷���ƂɎ��g�݂܂����B���̌��ʁA�������Ԃ͕���7����3���ɉ��L���A���r�o���͖�4���ԁA�������̓��w����52��Ɍ������܂����B�����҂͓����̊����ʂ��啝�ɑ����A�Ԃ����ő����j�b�g�܂Ŏ���������A���̑��Ȃǂɂ��ӗ~�I�ɎQ������ȂǁA�ӎv�\���������ʂ������Ȃ�A�������\��L���ɂȂ�Ƃ������ʂ��݂��܂����v�B
�@�u����r�b�`�m�v�́A�C���J���A�������̓V�X�e���Ƃ��A�����Ă��邽�߁A����܂œ����҂���������ƁA�^�u���b�g��p�\�R���ɏ�����Ă������A���݂͒[�����m�F���Ȃ��Ă��C���J���ɉ����ŏ����A�����ɋ삯����K�v���f���đΉ����邱�Ƃ��ł��A�X�^�b�t�̕��S�y���ɂ��Ȃ����Ă���Ƃ����B
�@����ɁA�E���̍��ɗ\�h��Ƃ��ẮA�ڏ�T�|�[�g���{�b�g�u�g�����v�i������Ђe�t�i�h�j�ƁA�ړ����X�^���f�B���O���t�g�����A�ڏ�ɂ��g�̓I�ȕ��S�y����}���Ă���B�u�g�����v�́A�x�b�h����Ԃ����̈ڏ�A���ʊԈړ��A���ʕێ����T�|�[�g����@��ŁA�݂�グ���̃��t�g�Ƃ͈قȂ�A���p�҂̋r�͂����p�����ڏ����\�ƂȂ��Ă���B�����̋@��̓�����A���ɂ𗝗R�Ƃ������E�҂�1�l���o�Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�u���Ɩ��̌������ɂ��A�Z�k�������Ԃ͐H����r���Ȃǂ̒��ډ��ʃP�A�A�����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɏ[�Ă��邽�߁A�P�A�̎������߂邱�ƂɂȂ����Ă��܂��B�h�b�s�E��샍�{�b�g������ۂ̃|�C���g�Ƃ��ẮA�o�c�w����������@���V�X�e����I�肵�A�E���Ɏg�p�𑣂��̂ł͐Z�����܂���B�܂��͌���̉ۑ��E���Ƌ��L���邱�Ƃ���n�߁A�ۑ�̉��P��}��@��E�V�X�e����E���ƈꏏ�ɑI�肵�Ă������Ƃ��d�v���ƍl���Ă��܂��v�B
���͂���E��Â��肪�E���̊m�ہE�蒅�ɂȂ���
�@���{�݂́A�E����̉��P�ƂƂ��ɁA�h�b�s�E��샍�{�b�g�����p�����Ɩ��̌��������������Ă��邱�Ƃ��]������A�ߘa5�N�x�u���E���̓����₷���E����Â�����t������b�\���v����܂��Ă���B
�@����ɁA�A�E��]�҂ɑI��閣�͂���E��Â���Ɏ��g�ނ��Ƃɂ��A���X�^�b�t�͐��K�E���A�p�[�g�E���Ƃ��Ɉ��肵�Ċm�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă���Ƃ����B
�@�u�Ƃ��ɐV���̗̍p�ɂȂ����Ă���A�ߘa3�N�x��8�l�A4�N�x��7�l�̐V���҂��̗p���Ă��܂��B���債�����@���Ɓw�������̎d��������̂ł���A�Ő�[�̌���œ��������x�Ƃ������������A���{�݂Ƃ̍��ʉ��ɂ��A���Ƃ��ʋΎ��Ԃ������������Ă��W�Ȃ��ƍl����X�^�b�t�������X��������܂��v�B
�@�h�b�s�E��샍�{�b�g�����p����ȂǁA���͂���E��Â���𐄐i���铯�{�݂̍���̎��g�݂����ڂ����B�@
 |
|
| ���@�J�t�F�X�y�[�X��݂����n��𗬃z�[���B�n��Z���ւ̖����J�����s���Ă��� | ���@�}���X�y�[�X�ł́A�����҂͒���߂Ȃ���Ǐ����y���ނ��Ƃ��ł��� |
�Љ���@�l��������̕�����
������ ��� �L�s��
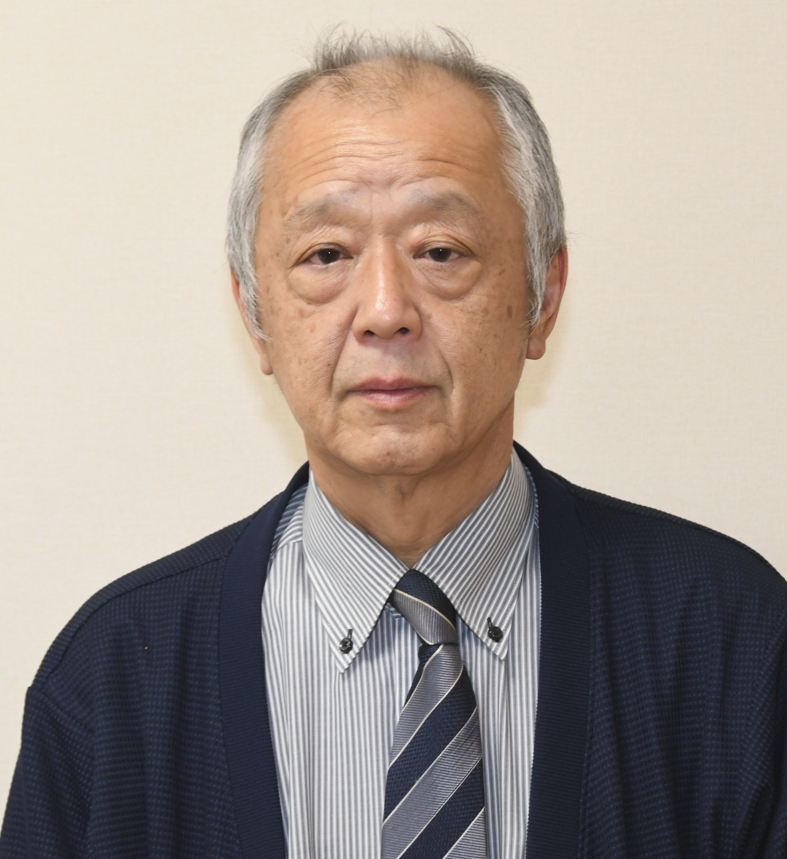 �@���@�l�́uDo��Think�v�i�Ƃ肠��������Ă݂悤�j���|���V�[�Ɍf���A�E���������I�Ɋ������A�@�l���������㉟������Ƃ����K�����Z�����Ă���A�ӗ~�I�Ƀ`�������W����E�ꕗ�y�����邱�Ƃ����݂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���@�l�́uDo��Think�v�i�Ƃ肠��������Ă݂悤�j���|���V�[�Ɍf���A�E���������I�Ɋ������A�@�l���������㉟������Ƃ����K�����Z�����Ă���A�ӗ~�I�Ƀ`�������W����E�ꕗ�y�����邱�Ƃ����݂ƂȂ��Ă��܂��B�@����̓W�]�Ƃ��ẮA���Ə��n�������Ə��̉^�c���O���ɏ悹�Ă����ƂƂ��ɁA�K�v�ɉ�����DX�EICT����i�߂Ă����\��ł��B�܂��A�V���Ɏ��ꂽ�E���ɑ��ẮA�Љ���@�l�Ƃ��Ă̖����ⓖ�@�l�̗��O�E�|���V�[��Z�������Ă������߁A�S�̂̐�������łȂ��A�����`�~�[�e�B���O��ʂ��đS�E���ƈӌ����������Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| ������ | ���@�L�s | �J�� | ����29�N8�� |
| ���ݎ{�� | ������x�����Ə��A�n���x���Z���^�[ | ||
| �@�l�{�� | ���ʗ{��V�l�z�[���A���V�l�ی��{�݁A�O���[�v�z�[���A���K�͑��@�\�^������A�f�C�T�[�r�X�Z���^�[2�J�� | ||
| �Z�� | ��939�|2226�@�x�R�s���[��237 | ||
| TEL | 076�|468�|1000 | FAX | 076�|468�|3001 |
| URL | https://osawano.com | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2024�N6�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B