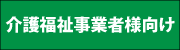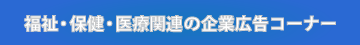サービス取組み事例紹介
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
| ▲ 施設の外観 |
精神科基幹病院として治療から地域生活まで支える
広島市西区にある医療法人社団更生会こころホスピタル草津は、広島県西部の精神科基幹病院として「いつも、あなたのそばに」というコンセプトのもと、地域に根ざした精神科医療を提供している。
法人の沿革としては、昭和8年に佐藤外科医院を開設したことに始まる。その後、草津病院に名称変更を行い、精神科救急医療施設として地域の救急医療を支える役割を担うとともに、広島市西部認知症疾患医療センターとして認知症の早期発見、周辺症状の治療などにも力を入れている。さらに、専門的な治療だけでなく、相談支援、訪問看護、自立訓練(生活支援)事業所、就労支援事業所を整備し、治療から地域生活まで包括的なサポートに取り組んでいる。
現在の病床数は429床で、その内訳は精神科救急急性期医療入院料が286床、精神病棟入院基本料が96床、認知症治療病棟が47床となっている。うつ病などの気分障害、統合失調症、認知症、アルコール依存症など、あらゆる精神疾患に対応している。
地域における精神科の医療提供体制としては、県西部の精神科救急輪番病院は2施設のみで、身体疾患や認知症慢性期の診療を行う病院は比較的充実しているものの、合併症に対応できる病院が少なく、精神科救急や合併症、認知症急性期の医療ニーズが高くなっており、同院が地域で担う役割が大きくなっている。
 |
 |
| ▲ こころホスピタル草津の総合受付と診療室 |
地域とつながる精神科病院を目指して
同院は、令和6年8月に本館となる新棟を開設するとともに、病院名を「草津病院」から「こころホスピタル草津」に改称している。
病院名を改称した経緯について、理事長・院長の佐藤悟朗氏は次のように説明する。
「平成30年に広島県で豪雨災害が発生し、災害派遣精神保健医療チーム『DPAT』に参加したことがきっかけでした。安否確認や診察をするため被災地に入りましたが、精神科への抵抗感から受診を拒否されるケースが多く、治療を必要とするにも関わらず、無治療の患者が地域にはたくさんいることに気づかされました。そこで精神科病院のもつ旧来のイメージを改善し、受診のハードルを下げるために病院名やロゴを明るく親しみやすいものに替えました。また、日頃から関わりがなければ、支援が必要なときに助けられないことを痛感したため、相談機能を充実させ、患者や家族、地域住民が立ち寄りやすくしています。精神科医療にとって、技術的なものだけでなく、イメージ的なものも治療の一つだと考えています」(以下「 」内は佐藤理事長の説明)。
新たに整備した8階建ての新棟(本館)は、茶色とグレーを基調とした商業施設のような外観にすることにより、精神科の閉鎖的なイメージを排除することに注力した。院内は外来部門や相談支援部門のスペースを広くとり、安全対策をしたうえでガラス窓を多く用いることで明るく開放的な空間をつくった。病棟の設計では、感染症に対応できるよう1病棟を4区域に分けることができる防火扉を設けるとともに、多床室をシンプルな四角形にすることにより、地域のニーズにあわせて病床形態を変更できる可変型の病棟機能を備えた。
そのほかにも、院内には職員専用の通路やバックヤードを多く設けることで、患者への迅速な対応や見守りなどの機能性を高めることにつながっているという。
 |
 |
| ▲ 明るく暖かみのある内装の病室とデイルーム |
相談機能の充実を図る
新棟の3階には医療福祉相談室や地域連携室などの相談機能を集約した地域支援センターを設置した。各種専門職や相談員による受診や入院、生活全般に関する相談、必要な行政サービスの情報提供を行っている。この相談機能の充実とともに、患者や家族、地域住民が自由に利用できるラウンジを設けることで病院に立ち寄りやすくする環境をつくった。
さらに、3階には最大収容200人の多目的ホールを設置し、講演会や研修、イベントなどに活用している。
「多目的ホールは、地域の団体や住民に無料で貸し出しており、日頃から気軽に病院に足を運んでもらい、関係性を構築することで精神科への受診のハードルを下げたいと考えています。また、8階は職員専用フロアとなり、見晴らしのよい職員食堂を設置しました。本当は患者や家族、地域の方にも利用していただきたいのですが、感染症の管理が難しいことから、職員専用としています」。
職員食堂は、食事の場としての利用だけでなく、職員同士のコミュニケーションや自習など、幅広い目的で活用されており、職員からも好評だという。
 |
 |
| ▲ 3階には相談機能を集約した地域支援センターを設置。患者は診療の待ち時間にラウンジで過ごすことができる | |
 |
|
| ▲ 最大200人を収容できる多目的ホールは、研修やイベントなどに活用するほか、地域住民に無料で貸し出しを行う | |
 |
 |
| ▲ 8階にある職員食堂は、市内や瀬戸内の島々を一望することができる。職員同士のコミュニケーションの場としても活用されている | |
地域医療を支える最後の砦としての救急
同院が実践する精神科医療の特色としては、救急医療では24時間365日体制で患者を受け入れ、救急搬送の受け入れ数は年間242件を超えていることである。入院医療では急性期の患者に対して、密度の高いチーム医療を実践し、短期集中的な質の高い治療を提供している。
救急医療の方針としては、「受け入れを断らない」ことを徹底しているという。
「精神科の救急はワンチャンスであることが多く、例えば、深夜に状態が悪化した無治療の患者に『明日まで待ってください』と伝えると、翌日に受診することはまずありません。そのときに対応しなければ、次の受診が10〜20年先になる可能性もあります。単に具合の悪い患者を診るのではなく、『地域医療を支えていくうえでの最後の砦としての救急』ということが当院の役割だと考えています」。
先進的な治療にも積極的に取り組んでおり、うつ病では脳を磁気で刺激することで症状を緩和させる治療法「rTMS」(反復経頭蓋磁気刺激療法)や、全身麻酔をしたうえで電気刺激を与える治療法「m-ECT」(修正型電気けいれん療法)を実施。そのほかにも、クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療薬)、LAI(持続性注射剤)など、新薬による投薬治療を行っている。
これらの取り組みにより、同院の平均在院日数は90日前後と、全国平均(令和5年度:精神科病床の全国平均263.2日)の3分の1となっている。
退院後の地域生活をサポート
このように高水準を維持できている要因としては、質の高い治療とともに地域生活支援を充実させていることが大きく、そのようなサポート体制がなければ救急を回すことはできないとしている。
地域生活支援では、障害のサポートや現状の生活維持だけでなく、次のステップを目指し、長期的な視点で社会生活の満足度や充足度を向上させる支援を行っている。デイケアなどの外来リハビリテーションや患者自身が選択できるプログラム等を用意することで、意欲的に取り組んでもらうことにつなげている。
さらに退院後のサポート体制では、ライフサポート館に相談支援事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援・就労継続支援B型事業所などの地域生活を支える機能の集約を予定している。
就労支援の取り組みの一つとしては、就労継続支援B型事業ではJA安芸との農福連携で、統合失調症の患者を中心に利用者16人が農作業に取り組んでいる。
JAとの連携によるメリットとしては、利用者が農業の専門的なスキルだけでなく、社会人としての指導を受け、社会構造を知ることができることをあげている。
「収穫した作物はJAの販売所や院内で販売していますが、障害者が栽培した作物として販売するのでは次につながりませんし、一般就労を目指すためにも一般の市場で通用する高い品質にこだわっています。そのほかにも、就労継続支援B型事業では、院内にあるコンビニエンスストアで利用者7人を雇用しています。コンビニの業務を行う就労継続支援B型事業所は全国でも少ないのですが、接客や品出し、調理など、さまざまな業務を体験することができます。訓練を積むことで地域のコンビニでも雇用が広がる可能性がありますし、人材が不足するコンビニ業界にも貢献できると考えています」。
|
|
| ▲ 就労継続支援B型事業では、JA安芸との農福連携による農作業に取り組む |
地域で無治療の患者を医療につなげる
同院は、今後診ていきたい患者像として、治療が必要にもかかわらず受診に至っていない人たちを医療につなぐことをあげており、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいる。
「例えば、自宅がごみ屋敷のような状態で近隣トラブルを起こしていても、本人に病気の自覚がないケースがあります。関係性がないなかで私たちが出向いても受け入れてもらうことは難しいことから、普段からそのような人たちを見守っている地域の支援団体や関係者とネットワークを築くことで治療や支援につなげていきたいと考えています」。
具体的な連携体制としては、地域包括支援センターと相談支援事業所の担当者が毎月会合を開き、事例の共有や役割分担をしながら互いに紹介しあうことに取り組んでいる。
また、地域包括支援センター主催の「在宅医療・介護関係者の連絡会議」(年2〜3回開催)に参加し、構成メンバーの西区保健センターや民生委員、医療機関、介護施設、調剤薬局、福祉用具メーカーなどと顔の見える関係を構築し、地域の情報収集を行っている。
「支援者は、地域のさまざまな情報を把握しており、当院の患者の生活状況などの情報が入ってくることも非常に役に立っています。開催場所として当院の多目的ホールを提供していますが、最小限の労力で地域の関係者との関係性を構築することができ、さまざまな情報が集まるようになっています。近年は8050問題などが表面化し、家族全体を支援する機能が求められていますが、地域とのつながりを強化することで対応していきたいと考えています」。
地域に親しまれる病院づくりとともに、専門的な治療から地域生活まで包括的なサポートを行う同院の今後の取り組みが注目される。
医療法人社団更生会 こころホスピタル草津
理事長/院長 佐藤 悟朗 氏
 精神科医療の目指すべきところは、他の診療科と同じように病状がよくなれば医療から離れ、同年代の人たちと同等な生活を送れることだと考えています。しかし、精神科医療においては他の診療科に比べ、治療半ばでドロップアウトしてしまう患者のほか、地域には無治療の患者がたくさんいるという現状があります。
精神科医療の目指すべきところは、他の診療科と同じように病状がよくなれば医療から離れ、同年代の人たちと同等な生活を送れることだと考えています。しかし、精神科医療においては他の診療科に比べ、治療半ばでドロップアウトしてしまう患者のほか、地域には無治療の患者がたくさんいるという現状があります。今後も、社会的弱者の方や地域の医療ニーズに耳を傾けながら、さらに地域生活全般をサポートしていくことにより、患者の「精神科医療からの卒業を目指す」ことをコンセプトに運営していきたいと考えています。
<< 施設概要 >>
| 病院開設 | 昭和8年 | ||
| 理事長/院長 | 佐藤 悟朗 | ||
| 病床数 | 429床(精神科救急急性期医療入院料286床、精神病棟入院基本料96床、認知症治療病棟入院料47床) | ||
| 診療科 | 精神科、心療内科、神経内科、内科 | ||
| 法人施設 | 相談支援事業所、訪問看護ステーション、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援・就労継続支援B型事業所 | ||
| 指定施設 | 広島市西部認知症疾患医療センター、広島市西区障害者基幹相談支援センター | ||
| 住所 | 〒733-0864 広島県広島市西区草津梅が台10−1 | ||
| TEL | 082−277−1001 | FAX | 082−277−1008 |
| URL | https://www.kusatsu-hp.jp | ||
■ この記事は月刊誌「WAM」2025年4月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。
月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。