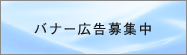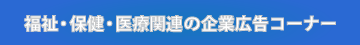制度利用に関する質問を掲載しています。
障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?
発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?
障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
障害福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか。
障害福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障害のある方の障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。
サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?
ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。
サービスの支給決定の際に用いられる障害支援区分とはなんですか。
知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用においても、身体障害のある方と同様に障害者手帳を持っていないと、サービスを受けられないのでしょうか?
現在、サービスを利用していますが、他の市区町村に引っ越しをしました。障害福祉サービスの支給決定を受ける市区町村は変更になりますか?
介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?
サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。
同時に受けられないサービスの組み合わせはありますか?
グループホームを利用していますが、さらにホームヘルプを利用することはできますか?
外部サービス利用型のグループホームであれば、利用することができます。
障害支援区分の認定結果やサービスの支給決定の内容に不服がある場合はどうすればいいですか?
市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定などの内容に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。障害者介護給付費等不服審査会は、審査請求の事件を取り扱う専門機関です。障害者介護給付費等不服審査会は、2012(平成24)年4月より、地域相談支援給付費等にかかる審査請求も行うことになりました。
障害福祉サービスに関する苦情がある場合はどうすればいいですか?
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための機関で、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律または医療に関して学識経験を有する者で構成されています。
障害者総合支援法が施行されるまでの間において行われた障害者自立支援法等の改正について教えてください。
改正の概要は以下の通りです。
・利用者負担について応能負担を原則とする。
・発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化。
・市区町村に基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制を強化。
・障害児支援について、障害種別等で分かれている施設を一元化。
・障害児通所支援の創設 など
2012(平成24)年4月から障害福祉サービスの利用者負担の仕組みが変わったと聞きました。どのように改正されたのですか?
障害者福祉制度における相談支援の強化がはかられたそうですが、具体的に教えてください。
基本相談支援では、地域の障害のある方の福祉に関する問題について、障害のある方やその保護者などからの相談に応じ、情報の提供および助言を行い、市区町村および指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整などを総合的に提供します。
地域相談支援では、障害者支援施設等に入所している障害のある方や精神科病院に入院している精神障害のある方に対する住居の確保や地域生活に移行するための相談支援(地域移行支援)、居宅において単身生活をする障害のある方に対する常時の連絡体制を確保するなどの相談支援(地域定着支援)を提供します。
また、計画相談支援では、サービスの利用計画案を作成し、その内容を反映した利用計画を作成し、継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、見直しなどを行います。
「支援費制度」以降の動向について教えてください。
従来、障害者福祉サービスの利用は、行政による「措置」が中心でしたが、2000(平成12)年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」が公布され、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の改正が行われました。「措置」から契約による「利用制度」へと変更することを主な内容としたものでした。
そして、2003(平成15)年から、障害のある方の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障害のある方自らがサービスを選択して事業者と対等の関係に基づく契約によりサービスを利用する「支援費制度」が始まりました。
しかし、支援費制度では、精神障害のある方が対象となっていなかったこと、障害種別ごとの制度になっていること、施設が細分化されていることなどの問題は解決されないできました。そこで、これらの課題を解決するとともに、障害のある方本人を中心とする個別の支援を、より効果的・効率的に行っていくため、2005(平成17)年10月に障害者自立支援法が成立し、2006(平成18)年4月より段階的に施行されました。さらに障害者自立支援法が改正され、2013(平成25)年4月より「障害者総合支援法」が施行されています。
発達障害のある方に対する支援について教えてください。
こうした状況を受け、2004(平成16)年12月に「発達障害者支援法」が成立しました。この法律では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義づけし、早期発見で適切なケアが行えるよう、国と地方自治体に対して総合的な支援を義務付けています。
また、発達障害のある方やその家族に対する専門的な支援や、医療・保健・福祉・教育・雇用など複数の分野にわたる総合的な支援を行うための中核的な機関として、「発達障害者支援センター」が全国に設置されています。
発達障害のある方は、障害者総合支援法における「障害者」の定義に含まれていますので、同法に基づくサービスの対象になっています。
障害者虐待防止法について教えてください。
虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した場合、どうしたらよいですか?
障害者雇用率制度について教えてください。
障害のある方の財産や権利を守り、安心して日常生活を送るための援助制度には、どのようなものがありますか?
障害のある方や障害のある児童への手当にはどのようなものがありますか?
障害のある方のための年金制度は、どのようなものですか?
障害者優先調達推進法について教えてください。
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、どのようなものがありますか?
障害者手帳を取得するにはどのように申請すればよいですか?
身体障害者(児)の現状を教えてください。
知的障害児(者)の現状を教えてください。
精神障害者の現状を教えてください。
監修者 山本雅章 調布市 子ども生活部部長
鈴木雄司 東京福祉大学社会福祉学部 保育児童学科教授