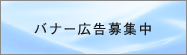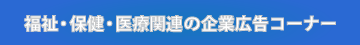制度利用に関する質問を掲載しています。
児童福祉サービスの対象は何歳まででしょうか?
児童相談所にはどんな役割がありますか?
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基いて各都道府県・指定都市に設置(中核市も設置可能)される児童福祉の専門かつ中核機関です。法律上の名称は児童相談所ですが、都道府県等によっては呼称が異なる場合があります。
医師、児童福祉司、児童心理司といった専門の職員が配置されており、虐待、育児、健康、障害、非行など、子どもに関するあらゆる相談に応じます。また、調査や判定を行い、必要に応じて一時保護や児童福祉施設への入所措置、子どもと保護者への相談援助活動なども行っており、児童虐待については中心的な役割を担います。
2014(平成26)年4月現在で、全国に207か所の児童相談所があります。
児童福祉司について教えてください。
家庭支援専門相談員とはどのような職種ですか?
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、児童相談所との密接な連携のもと、入所児童の早期家庭復帰、里親委託等を目的として相談・指導を行います。乳児院や児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置が義務づけられています。資格要件は社会福祉士、精神保健福祉士、施設において5年以上従事した者または児童福祉司の任用資格を有する者とされています。
児童虐待への対応として、まずはどんなことが必要ですか?
一時保護は、児童相談所長や都道府県知事の判断により、児童相談所の一時保護所や児童福祉施設、警察署などにおいて行われます。その後、児童相談所などにおいて調査や今後の対応策がとられていきます。
虐待した親から子どもを守りたい
子どもの虐待は、どのような親子にも起こる可能性があります。虐待の疑いがある家庭を見つけたら、速やかに市区町村や児童相談所に連絡しましょう。
児童虐待に関する相談や通報を受けた場合はその家庭を訪問し、安全を確認したり、子どもを緊急に保護する必要がある場合には、一時的に保護する措置が図られています。
しかし、虐待をする親の中には、しつけだといって虐待を認めない場合など親権が子どもの利益を害する場合には、児童相談所には期限付きで親権を制限できる「親権停止制度」や親権喪失などの請求を家庭裁判所に対し行うことができます。また同様にこども本人や未成年後見人なども請求できます。子どもの利益がもっとも優先され考慮されています。
隣家からよく、怒鳴り声や子どもの泣き声が聞こえてきます。もしかしたら虐待されているのかもしれませんが、間違いで通報すれば迷惑になります。こうした場合、通報の義務はありますか?
里親とはどんな制度ですか?
里親になることを希望する方は、まず児童相談所に相談します。適性や資格要件などの審査を通じて可否の判断がなされ、認定を受けたら里親として登録されます。そのうえで、子どもと里親のマッチングなどを考慮して委託が行われます。里親は、児童福祉司などの指導や援助を受けつつ子どもを養育し、その費用として委託費が支給されます。
「学童保育」とはどんなものですか?
仕事などの事情により保護者が昼間に家庭にいない小学生児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全育成を図ることです。児童福祉法上は「放課後児童健全育成事業」として位置づけられており、地域の実情に応じて行うよう努めることとされています。「放課後児童クラブ」と呼ばれることが多いですが、地域により別の名称で行われている場合もあります。生活の場として一定の基準を満たす専用のスペースで行われ、職員として放課後児童支援員が配置されています。利用料は、実施主体や保護者の所得により異なります。
今年子どもが小学生になります。共働きのため学校が早く終わり、夕方まで留守番させるのが心配です。
地域の実情に応じ放課後児童クラブ等を利用することが出来ます。保護者が仕事で昼間いない家庭で、1年生から6年生まで子どもたち(放課後児童)が、学校が終わった後に利用することができます。児童館や学校の空き教室等、市区町村や民間、父母会、NPO法人などが運営しています。詳しくはお住まいの市区町村にお問合せください。
障害の早期発見のために、乳幼児期の対策としてどんなことが行われていますか?
子どもでも身体障害者手帳を取得することはできますか?
障害児保育を利用したいのですが、どうすればよいでしょうか?
保育所によっても実施の有無に差がありますので、入所を希望する場合は、市区町村の担当窓口(福祉事務所、保健センター)に相談してみるのがよいでしょう。
子どもの問題で、最近では「発達障害」という言葉を耳にしますが、どういった子どもたちのことをいうのでしょうか?
「発達障害」とは、脳の機能的問題によって生じる障害のことを指します。2005(平成17)年から施行された「発達障害者支援法」では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義していますが、主なものを例示すると次の通りです。
・高機能自閉症・アスペルガー症候群(アスペルガー障害)
知的障害は伴いませんが、三つ組の障害(社会性・コミュニケーション・こだわりの障害)という自閉症の特徴的な障害がみられます。
・学習障害(LD)
知的障害が伴いませんが、読んだり、書いたりする特定の学習能力に障害があるものです。単に勉強不足や怠けているものとは異なりますが、大人になるまで誤解され続ける場合もあります。
・注意欠陥多動性障害(ADHD)
本人の意思によるコントロールが難しい、多動、衝動的な行動、注意集中の困難を中心とした障害です。
従来はいわゆる障害の範囲には含まれておらず、支援を受けにくい存在でしたが、この法律により徐々に支援の幅が広がりつつあります。現在では、障害のある方へサービスを提供する「障害者自立支援法」の対象にもなっています。
養育医療とは何ですか? 自立支援医療とは異なるのでしょうか?
養育医療とは母子保健法に基づくもので、養育のため病院・診療所に入院する未熟児に対し、市町村が必要な医療の給付を行い、または養育医療に要する費用を支給するものです。一方、自立支援医療は障害者総合支援法に基づく公費負担医療であり、障害児を対象とする育成医療、身体障害者に対する更生医療、精神障害者に対する精神通院医療があります。
子どもが難病にかかっているとの診断を受けました。何らかの支援策や利用できるサービスは何がありますか?
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾患の場合は、医療費の助成を受けることができます。この制度は、治療費(保険適用分)の自己負担分のうち一定の限度額を超える分を国が負担するものです。対象となる疾患は、「悪性新生物」「慢性腎疾患」「慢性呼吸器疾患」「慢性心疾患」などであり、重症患者と認定された場合には医療費の自己負担がありません。また、在宅で療養している場合には、特殊マット、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)などの日常生活用具の給付を受けることができます。
その他に、希望者には「小児慢性特定疾患児手帳」の交付も行っており、日常健康管理、緊急時の対応、周囲への啓発などに役立ちます。医療費の助成については保健所等、日常生活用具の給付については市区町村が相談・申請の窓口になっています。
子どもについて国からもらえる手当にはどんなものがありますか?
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などがあります。(※手当額は平成29年度の金額)
・児童手当は、0歳から中学校卒業までの児童に対して支払われます。
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき5,000円が支給されます。
・児童扶養手当は、児童を扶養しているひとり親家庭へ支給されます。また、配偶者からのDVで「裁判所からの保護命令」が出された場合にも給付されます。(27年4月から変更)
子ども1人の場合 全部支給 42,330円
一部支給(所得に応じて)42,320~9,990円
2人以上の加算 2人目 最大10,000円、3人目以上1人につき 最大6,000円が支給されます。
・特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある満20歳未満の児童に支給されます。所得による支給制限があります。(27年4月から変更)
1級 1人51,450円 2級 1人34,270円
・障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害を有する児童に対して給付されます。所得による支給制限があります。
月額 14,580円
初めての赤ちゃんがうまれました。近所に親や友人もおらず色々と不安です。どこか相談できるところがないか教えて下さい。
・子育てひろば:親子の交流の場や読み聞かせなど
・子育て支援センター:子育て教室、発達相談、栄養相談、悩み相談等
・保育所:園庭解放、子育て相談、育児講座、交流保育、一時預かり等
・児童館:育児相談、遊びの場の提供など
赤ちゃんに対するサービスにはどんなものがありますか?
市区町村では、「こんにちは赤ちゃん事業」で、生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭を保健師・助産師が訪ね、育児に関する不安や悩みを聞いたり、子育て支援に関する提供を行っています。また、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼになどの問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭には、育児支援や家事援助等を受けるサービスがあります。未熟児や多胎児は、育児支援・栄養指導を受けられます。お住まいの市区町村へお問い合わせください。
幼稚園と保育園(保育所)の違いとは何ですか?
幼稚園は学校教育法に基づく「学校」に分類され、3歳ごろから小学校入学までの幼児の保育を行います。保育所、いわゆる保育園は児童福祉法に基づく「児童福祉施設」です。子ども子育て支援法では、保育所と同じように、市町村の確認を受けた幼稚園についても市町村が認定(1号認定)することにより給付の対象となります。また保育所では、母子家庭や共働きの子どもなど、「保育を必要とする子ども」に対しての保育が行われます。近年では幼保一体化の観点から、保育所保育指針と幼稚園教育要領との内容の整合性が図られています。
認可保育所と無認可保育所の違いは何ですか?
認定こども園とはどんなところですか?
保育所への待機児童の実態を教えて下さい。
子どもが3歳になったので、パートで週に何日か働こうと考えています。どこか預かってくれるところはありますか?
育児休暇をとって子育て中の母親です。もうすぐ子どもが1歳になるのですが、預けられる保育所が見つかりません。育児休暇はどのくらい延長できるのでしょうか?
家の近くに地域子育て支援拠点があります。子どもが遊んでいますがどんなところなんですか。
児童養護施設を退所したあと、アパートを借りたいのですが、保証人はどのようにして探せばよいでしょうか?
地域小規模児童養護施設とは何ですか? 一般の児童養護施設と何が異なるのでしょうか?
「犯罪少年」「触法少年」「虞犯少年」の違いについて教えてください。
監修者
鈴木雄司 東京福祉大学社会福祉学部 保育児童学科教授
山本雅章 調布市 子ども生活部部長