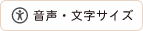

目次


一般の住民から選ばれ、地域の人々を見守り手助けする
民生委員は、一般の住民から選ばれた、地域の人々が暮らしやすくなるための手助けをする人です。具体的には、地域でひとり暮らしをしている高齢者など、困りごとが生じがちな人々を見守り、相談にのったり助言を行ったりします。何かの手助けが必要な人には、専門的な支援ができる機関につなげたりもします。
特に、子どもや妊娠中・出産したばかりの親を対象とした手助けを行う人を「児童委員」といい、民生委員がかねています。

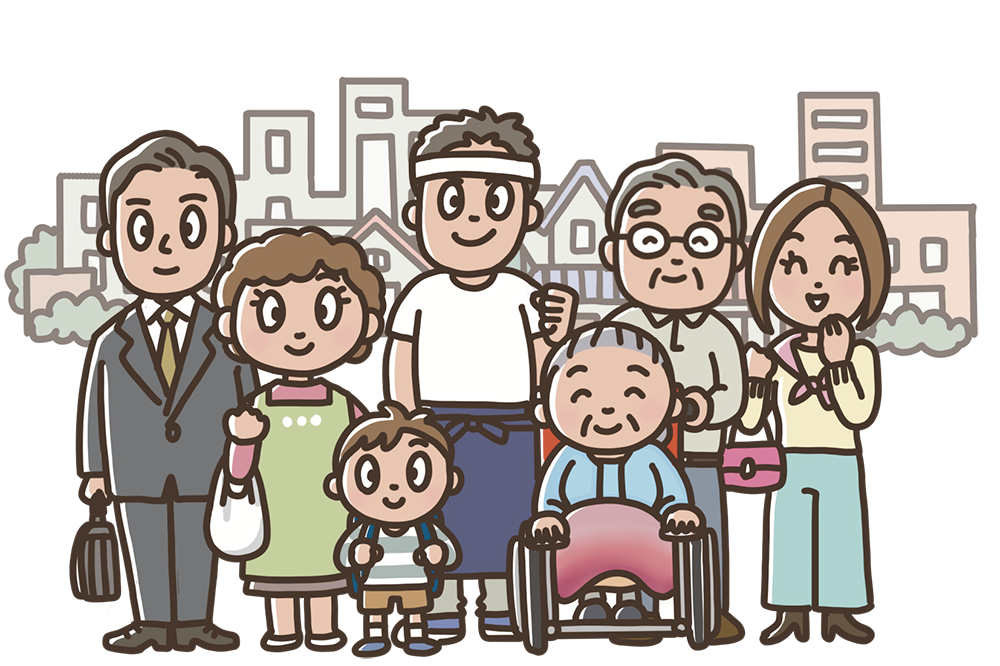
自分が住んでいる地域で、家々を訪問するなど
その民生委員・児童委員本人が住んでいる地域で、担当区域の家や人を訪ねながら、見守りや援助を行っています。
現状は、主に定年退職した人や子育てを終えた主婦、地域でボランティア活動などを行っている人などが、役所から民生委員・児童委員の活動を任されてなることが多いようです。


ひとり暮らし高齢者の多い地域での民生委員・児童委員の場合
-
- 9:00
-
その日の訪問先を決める家を出る前に、自分の担当のエリアをしっかり回れるように計画を立てる
-
- 9:30
-
健康づくりのチラシなどを持って訪問スタート
 ワンポイント解説訪問先での話のきっかけになる、健康づくりのパンフレット、特殊詐欺や消費者被害への注意を呼びかけるチラシなどを持って、配りながら訪問
ワンポイント解説訪問先での話のきっかけになる、健康づくりのパンフレット、特殊詐欺や消費者被害への注意を呼びかけるチラシなどを持って、配りながら訪問
-
- 10:30
-
困りごとがあるAさんの玄関で相談を受ける
 ワンポイント解説Aさんの困りごとの解決にどのような支援が必要か、どこに相談すればいいか、アドバイスを行う
ワンポイント解説Aさんの困りごとの解決にどのような支援が必要か、どこに相談すればいいか、アドバイスを行う
-
- 11:00
-
Aさんの困りごとについて、福祉事務所に連絡Aさんの了承を得たので、支援の入口となる機関に連絡
-
- 12:00
-
昼食、休憩
-
- 13:00
-
地域の高齢者サロン(居場所)に出向き、話し相手のボランティアサロンの参加者のひとりが、話しているうちに、「相談にのってもらいたい」と希望したので、相談を聞く
-
- 14:00
-
児童委員として、生まれたばかりの赤ちゃんがいる家を訪問
 ワンポイント解説地域の子育てサロンのチラシを持って訪問。子育ての不安について、玄関先で少し立ち話
ワンポイント解説地域の子育てサロンのチラシを持って訪問。子育ての不安について、玄関先で少し立ち話
-
- 15:00
-
地域支援ネットワークの会議に出席
 ワンポイント解説行政の担当者から「地域にどんな支援があるといいか?」と訪ねられたので、個人情報に注意しながら、「こんなふうに困っている人が多いようだ」と自分の実感を伝える
ワンポイント解説行政の担当者から「地域にどんな支援があるといいか?」と訪ねられたので、個人情報に注意しながら、「こんなふうに困っている人が多いようだ」と自分の実感を伝える
-
- 16:30
-
町内会の会合に出席地域住民として出た町内会の場で出た高齢者に関する相談に、民生委員として対応
-
- 17:30
-
帰宅
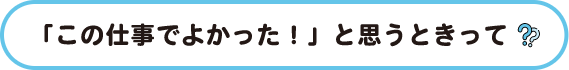
訪問を拒否されていた人が、相談ごとをもちかけてきたとき
・いつ訪問しても居留守だったが、ようやく話ができた
訪問を通じて、地域の人々の安全を守れたとき
・新聞がたまっていたので、担当のケアマネジャーに連絡したら、転倒して動けなくなっていた本人を発見。命をとりとめた
行政の人に地域の課題を伝え、新たなしくみができたとき
・地域のスーパーがなくなり買い物に困っている人が多いと伝えたところ、業者と協力して訪問販売のしくみができた
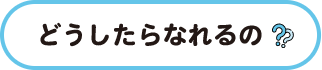
20歳以上で、市区町村議会議員の選挙権をもつ人の中から推薦
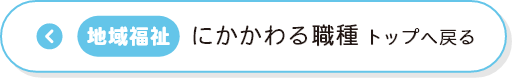

福祉のしごとガイドトップへ戻る














