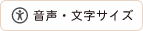

目次


障がいがある人の地域生活を支えるサービスの相談や手配
体の障がいや知的障がい、精神の障がいなどがある人は、地域で自分らしく暮らすために、障がい福祉サービスなどの手助けが必要になることがあります。こうしたことに関する相談を受け、本人の思いを尊重しながらサービスを提案し、利用の計画を立てたり手配をしたりするのが、相談支援専門員です。
また、障害者施設に入所している人が、施設を出て地域で暮らしたいという場合、相談支援専門員が住宅に移るための手伝いもします。自分では住宅入居などの契約が結べない人に、代理をしてくれる人を見つける支援を行うこともあります。


障がいのある人にサービスの手配を行う指定相談支援事業所
障がいのある人からの相談を受け、サービスの計画を作成したり手配を行ったりする事業所を「指定相談支援事業所」といい、相談支援専門員は主にそこで働いています。地域の障がいがある人からのさまざまな相談にのる基幹型相談支援センターや、役所の障がい者支援の部署で働くこともあります。

指定相談支援事業所で働く相談支援専門員の場合
-
- 8:30
-
出勤、事業所内での申し送りその日の訪問などスケジュールも確認
-
- 9:00
-
障がいのあるAさんからの相談に対応
 ワンポイント解説事業所を訪問してきたAさんに、サービス利用計画の作成を依頼されたので対応
ワンポイント解説事業所を訪問してきたAさんに、サービス利用計画の作成を依頼されたので対応
-
- 10:30
-
サービス利用を希望するBさんの調査のために訪問サービス利用を希望するBさんの要望や暮らしの様子、障がいの状態などを調査するために、Bさんの自宅に訪問し面談
-
- 12:00
-
昼食、休憩
-
- 13:00
-
サービス利用を希望するBさんの計画の作成
 ワンポイント解説Bさんの思いを尊重し、サービスの手配をどのように行い、いつ・どのようなサービスを提供するか計画を作る
ワンポイント解説Bさんの思いを尊重し、サービスの手配をどのように行い、いつ・どのようなサービスを提供するか計画を作る
-
- 14:00
-
Cさんの自宅でサービス担当者会議を開く
 ワンポイント解説Cさんにサービス利用計画の案を示して、Cさん本人やご家族、実際にサービスを提供する担当者からの意見を聞く
ワンポイント解説Cさんにサービス利用計画の案を示して、Cさん本人やご家族、実際にサービスを提供する担当者からの意見を聞く
-
- 15:30
-
入所施設から出るDさんのための支援を打ち合わせ
 ワンポイント解説入所施設からの依頼を受け、地域での暮らしに移るDさんのための支援について、いくつかの機関に出向いて打ち合わせ
ワンポイント解説入所施設からの依頼を受け、地域での暮らしに移るDさんのための支援について、いくつかの機関に出向いて打ち合わせ
-
- 16:30
-
サービス利用を始めたEさんの様子を確認
 ワンポイント解説Eさんを訪問して、その後スムーズにサービスが利用できているか、Eさんの思いがかなえられているかどうかなどを確認
ワンポイント解説Eさんを訪問して、その後スムーズにサービスが利用できているか、Eさんの思いがかなえられているかどうかなどを確認
-
- 17:30
-
その日の相談内容を整理・記録、事業所で今後の支援を検討その日に寄せられた相談内容について事業所内で話し合い、今後どのような支援を行えばいいかを検討
-
- 18:00
-
終業
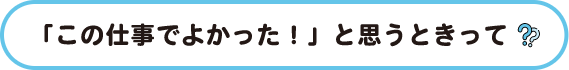
施設から出た人が、望みどおりひとり暮らしができているとき
・地域で友人ができて、気持ちが晴れやかになったと言われた
・金銭管理が不安だったが、支援のおかげで普通に過ごせている
障がいがある人の家族の悩みが軽くなったとき
・家族から「相談できる人がいて心が軽くなった」と言われた
・家族が突然障がい者になり途方にくれていたが、助かったと言われた
さまざまな支援機関の専門職とのつながりが広がったとき
・住居支援などでわからないことを気軽に相談できる機関ができた
・病院の相談員とつながりができて、情報入手が楽になった
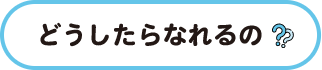
3〜10年の仕事の経験+相談支援従事者初任者研修を受ける
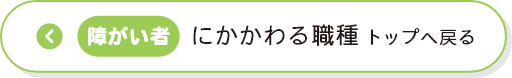

福祉のしごとガイドトップへ戻る


















