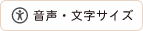

目次


障がいのある子どもたちを教育する仕事
体の障がいや知的な障がいがある子どもたちに、ハンディキャップを補いつつ、生活するうえで必要な知識や技術を教える仕事です。
さまざまな障がいに関する基本的な知識を備え、子どもたち一人ひとりの教育上の望みにこたえるための技術をもっています。
また、学習障害や注意欠如多動性障害など、学習や生活のしづらさに悩む子どもたちの就学サポートをすることも増えています。


ハンディキャップのある子どもたちが通う特別支援学校
主に、体の障がいや知的障がいがある子どもたちが通う特別支援学校で働いています。
また、小・中学校の中にあり、ハンディキャップのある子どもたちが学ぶ教室である特別支援学級でも働いています。



特別支援学校で働く特別支援学校教諭の場合
-
- 8:00
-
出勤、ほかの教諭との打ち合わせ親からの連絡事項がある場合は、全員で確認
-
- 8:30
-
登校してくる子どもたちに対応あいさつをしながらその日の子どもたちの様子を確認
朝の体操で体を動かす
-
- 9:00
-
国語・算数などの授業を行う数字のパズルやひらがなのなぞり書きなど、一人ひとりに合わせたカリキュラムやグループで授業する
-
- 10:00
-
休み時間、トイレのサポート1人でトイレできるように練習をすることもある
-
- 10:30
-
生活単元学習料理や園芸などを通して、生活に必要な知識や技能を身につける学習をする
-
- 11:30
-
給食手洗いや配膳、食べ方などを伝える
-
- 12:30
-
後片づけ、歯みがき食器の片づけや教室内の掃除、歯みがきなどの必要な生活習慣を伝える
-
- 13:00
-
昼休み一人ひとりの過ごし方をよく観察し、付きそう
-
- 13:30
-
自立活動の支援それぞれの子どもの特徴に応じて暮らしやすくするための「自立活動」を行う
-
- 14:30
-
下校の準備忘れ物や着替えの確認を手伝う
-
- 15:00
-
子どもたちが下校放課後デイサービスに行く子どもには、その事業所に連絡し、情報共有を行う
-
- 16:00
-
職員会議や勉強会
 ワンポイント解説その日の子どもたちの様子について共有
ワンポイント解説その日の子どもたちの様子について共有
または職員同士で勉強会
-
- 17:00
-
その日の支援の記録や翌日の計画などを作成生活単元学習や自立活動について、翌日の計画を立てる
-
- 18:00
-
終業
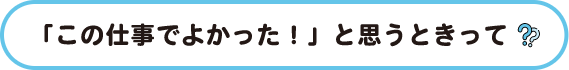
生徒が自ら進んで活動を行うようになったとき
・生活単元学習で、率先して同級生と協力するようになった
親から、生活習慣が身についてきたと聞いたとき
・脱ぎ散らかした衣服を自分でまとめるようになったと聞いた
地域の人たちの理解が深まり、交流の機会が増えたとき
・地域清掃のときに、地域の人が協力してくれるようになり、子どもたちと一緒に行えた
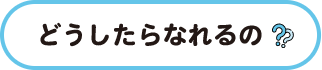
特別支援学校教員を養成する大学などを卒業し、免許を取得
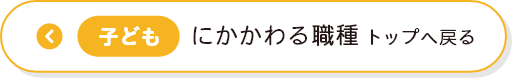

福祉のしごとガイドトップへ戻る


















