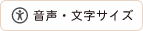

児童発達支援事業所
目次


障がいのある子どもたちに通ってもらい、身の回りをサポート
さまざまな障がいのある子どもたちは、大人になったときに社会で自立して生きていけるように、それぞれの状態に合わせた支援をする必要があります。その支援を「療育」といい、児童発達支援センターや障害児入所施設などで行われています。これらの施設をまとめて、「療育センター」と呼ぶことがあります。
障害児入所施設が「そこに入所して暮らす」のに対し、児童発達支援センターは、一部訪問サービスを提供することもありますが、原則的に「そこに通って過ごす」場所です。地域で自立した生活を送るための知識や技能を身につけてもらったり、集団での生活になじむための練習もします。身の回りや生活の手伝いなどが中心となるのは「福祉型児童発達支援センター」といい、医療的なケアも行うのは「医療型児童発達支援センター」といいます。
一方、児童発達支援センターより多くあり、より身近で通いやすい地域の療育の場所が、「児童発達支援事業所」です。


障がいのある1歳から小学校入学前の子どもたち
体に障がいがあったり、知的な障がいがある1歳から小学校入学前までの子どもが対象です。障がいのある子どもがいる親から子育てなどの相談を受けたり、助言を行ったりもします。
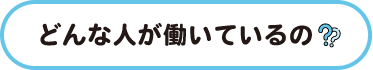

身の回りの手伝いや支援を行う保育士・児童指導員が中心
障がいのある子どもたちが健やかに成長できるよう、主に、身の回りの手伝いをする保育士や、自分でできることを増やすための支援を行う児童指導員が働いています。一人ひとりの子どもに合わせた支援の計画を立てる児童発達支援管理責任者もいます。
そのほかにこんな人も!

児童発達支援事業所で働く児童指導員の場合
基本的に日勤のみで、夜勤や宿直はありません。
-
- 8:00
-
出勤、その日に通ってくる子どもの情報を共有親からの連絡事項を全員で確認
-
- 9:00
-
通ってくる子どもたちを受け入れあいさつしながらその日の体調などをチェック
着替えやトイレをサポート
-
- 9:30
-
一人ひとりの子どもに個別のプログラムを行う
 ワンポイント解説児童発達支援管理者がまとめた計画に従い、職員で打ち合わせした子どもの成長を後押しするレクリエーションや課題などを行う
ワンポイント解説児童発達支援管理者がまとめた計画に従い、職員で打ち合わせした子どもの成長を後押しするレクリエーションや課題などを行う
-
- 11:00
-
食事前の手洗い、身の回りの片づけなど
 ワンポイント解説プログラムで使った道具の片づけや食事前の手洗いなどで、生活習慣を身につける練習をしてもらう
ワンポイント解説プログラムで使った道具の片づけや食事前の手洗いなどで、生活習慣を身につける練習をしてもらう
-
- 11:30
-
子どもたちの昼食の見守り食事のとり方を伝えるため、そばで付きそう
-
- 13:00
-
食後の歯みがき、昼寝の付きそい子どもたちの昼寝の間、職員は交替で休憩
-
- 14:00
-
学校生活のための動作・習慣づけの 練習
 ワンポイント解説小学校に上がる直前の子どもに、集団生活に早くなじめるようになるための練習を行う
ワンポイント解説小学校に上がる直前の子どもに、集団生活に早くなじめるようになるための練習を行う
-
- 15:00
-
子どもたちのおやつ、トイレのサポートおやつを食べながら話し、子どもたちがどんなことに関心や興味をもっているのか聞く
-
- 15:30
-
体を動かすため、曲に合わせてダンストレーニング将来の集団生活などに活かすため、皆でリズムを合わせて体を動かす。障がいがあり体の動きが限られている子どもには、理学療法士が付きそい、動かせる範囲で安全に動くような動きを指導してもらう。
-
- 16:30
-
帰宅する子どもたちの送り出し1日過ごした子どもたちが疲れていないか、体調に気を配る
-
- 17:00
-
後片づけや記録の作成、明日の打ち合わせなど
 ワンポイント解説それぞれの子どもたちの支援計画について、児童発達支援管理責任者と話し合う
ワンポイント解説それぞれの子どもたちの支援計画について、児童発達支援管理責任者と話し合う
-
- 18:30
-
終業


体の障がいや知的障がいがある子どもたちが通い、身の回りの生活を手伝ったり、少しでも自分でできることを増やしていくための習慣づくりをする

障がいのある子どもが、地域の生活になじむためには、地域のさまざまな機関や家庭との協力が必要。こうして子どもとその周囲の機関や人々とのつながりを作ることも求められている

地域のさまざまな支援の機会につなげる調整を担う児童発達支援センターの役割に注目が集まっている
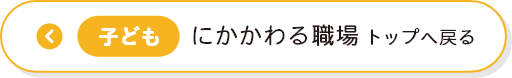

福祉のしごとガイドトップへ戻る











